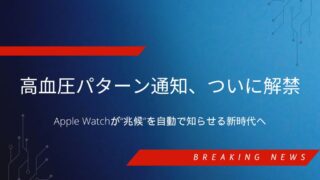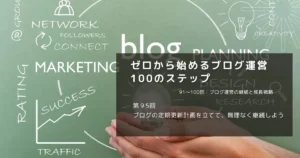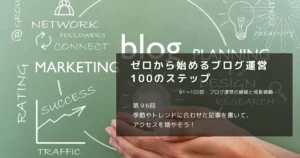GMKtec G9 FAQとは?
GMKtec G9は、NAS用途にも使える高性能なミニPCとして注目されています。 しかし、購入を検討している人の中には、以下のような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?
- 「本当にNASとして使えるの?」
- 「SSDの増設はどうやるの?」
- 「長時間運用しても大丈夫?発熱や電気代は?」
こうした疑問を解決するために、「GMKtec G9を購入する前に知っておきたい57の疑問と答え」 をQ&A形式でまとめました。製品のレビューは「GMKtec G9 レビュー!NASもOKな高性能ミニPCの実力を徹底検証」で紹介しています。
GMKtec G9について気になることがあれば、ぜひこのFAQを活用してください。
基本仕様・スペック
Q1. GMKtec G9のCPU(Intel N150)はどのくらいの性能?
A. Intel N150は、エントリークラスの省電力CPUで、軽作業には十分な性能を持っています。ただし、ゲーミングや動画編集などの高負荷な作業には向いていません。
📌 GMKtec G9のCPUスペック
- モデル名:Intel Processor N150
- コア / スレッド数:4コア / 4スレッド
- 基本クロック:1.0GHz / 最大クロック:3.6GHz
- TDP(消費電力):6W(超低消費電力)
- 内蔵GPU:Intel UHD Graphics(最大750MHz)
✅ こんな作業は快適
✔ ブラウジング(YouTube・SNS・ネット検索)
✔ 動画視聴(4K動画もスムーズに再生可能)
✔ Office作業(Word・Excel・Google Docs)
✔ 軽いプログラミング・リモートワーク
❌ 向いていない作業
✖ ゲーム(特に3Dゲームは厳しい)
✖ 動画編集・3Dレンダリング(GPUパワーが足りない)
✖ 大規模なデータ処理(AI学習や解析など)
📊 ベンチマークスコア(参考値)
実際の性能を他のCPUと比較すると、Intel N100はCeleronより高性能&Core i3より低性能なポジション
| CPU | シングルスレッド | マルチスレッド | TDP(消費電力) |
|---|---|---|---|
| Intel N150(GMKtec G9) | 750pts | 2600pts | 6W(超省電力) |
| Intel Celeron N5105 | 600pts | 2200pts | 10W |
| Intel Core i3-10110U | 1100pts | 3200pts | 15W |
| Intel Core i5-12400 | 1900pts | 9000pts | 65W |
📌 ポイント
- Intel N150はCeleronの上位互換的な性能
- 低消費電力(6W)なので、ファンノイズが少なく静か
- Core i3には届かないが、NASや軽作業用PCとしては十分なパフォーマンス
💡 まとめ:Intel N150の実力は?
✅ 日常作業はスムーズにこなせる
✅ NAS運用や省電力PCとしては最適
❌ ゲーミングや動画編集には向かない
Q2. メモリ12GBで足りる?増設はできる?
A. 12GBで日常作業やNAS用途には十分。ただし、増設はできないので注意しましょう。
📌 GMKtec G9のメモリ仕様
- 容量:12GB LPDDR5(オンボード)
- 規格:LPDDR5 4800MHz
- スロット:なし(増設不可)
📌 12GBで何ができる?
✅ 快適に動作する作業
✔ Webブラウジング(タブを10~15個開いても余裕)
✔ 動画視聴(YouTube・Netflix 4K再生OK)
✔ Office作業(Word・Excel・Google Docs)
✔ 軽いプログラミング(Python・VS Code など)
✔ NAS用途(ファイル共有・バックアップ)
❌ 厳しい作業
✖ 動画編集(Adobe Premiere・DaVinci Resolveなど)
✖ 高負荷なゲーム(メモリ使用量が多い3Dゲームなど)
✖ 大規模なデータ処理(仮想マシン・AI学習など)
📌 メモリ不足を感じるとしたら?
もし12GBで足りなくなるとしたら、以下のようなケースが考えられます。
- 複数のアプリを同時に立ち上げる(特にChrome+動画編集など)
- Windows 11でメモリ使用量が増加(アップデートによる負荷)
- Dockerや仮想環境(VMware, VirtualBox)を使いたい場合
📌 解決策
- メモリ使用量を抑える設定(バックグラウンドアプリを減らす・仮想メモリ設定)
- NAS用途ならUbuntuを使うとメモリ負荷が軽くなる
- 仮想環境を使いたいなら、メモリ16GB以上のミニPCを検討する
💡 まとめ:GMKtec G9のメモリは増設不可。でも、NAS用途や軽作業なら十分
✅ 日常作業やNAS運用なら問題なし
✅ 動画編集や仮想環境には不向き
❌ 購入後にメモリを増やすことはできないので、用途を考えて選ぼう
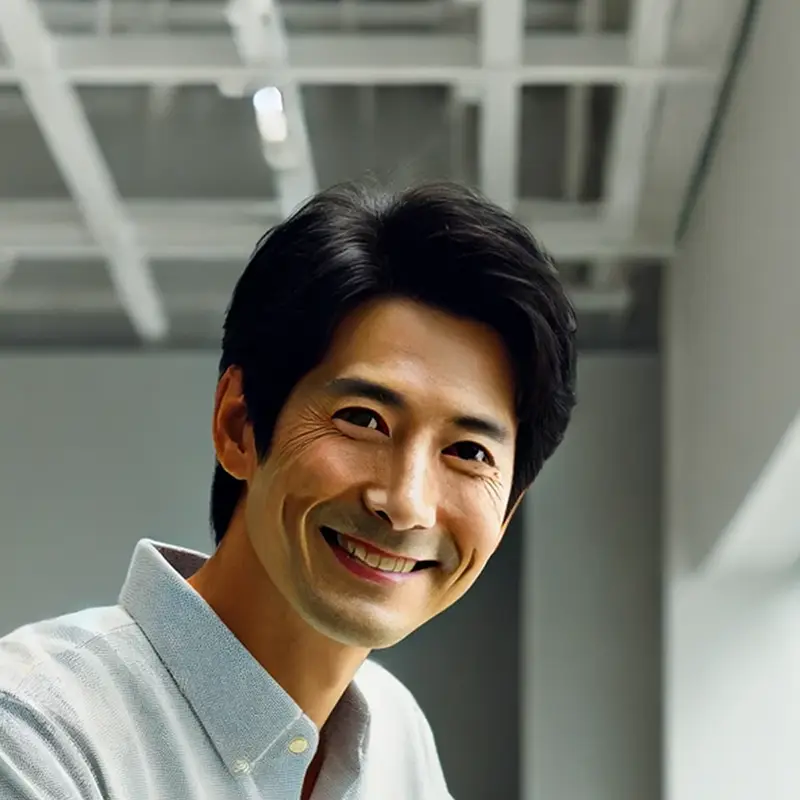
NAS用途を全然考えなくても、軽い作業なら全く問題ない。レビューしているG5も選択肢に入れるといい。「中古ノートPCの代わりに!? GMKtec G5を本音レビュー」をご参考ください。
Q3. M.2 SSDはどんなメーカーのものが使える?推奨SSDは?
A. GMKtec G9は「M.2 2280 PCIe 3.0 x2」規格のSSDに対応、SATAタイプのM.2 SSDは使えないので注意しましょう。
📌 GMKtec G9のSSD仕様
- 対応規格:M.2 2280(PCIe 3.0 x2)
- 非対応:SATA接続のM.2 SSD(Bキー / B+Mキー)
- 最大ストレージ容量:16TB(4TB × 4枚)
📌 推奨SSDメーカー&モデル
✅ コスパ重視(安くて信頼性のあるモデル)
✅ バランス型(速度と耐久性のバランス重視)
✅ 高性能&耐久性重視(長時間稼働するNAS向け)
📌 ポイント
✔ PCIe 4.0対応SSDも使用可能だが、GMKtec G9はPCIe 3.0 x2までの速度しか出ない
✔ NAS用途なら「耐久性(TBW)」が高めのモデルを選ぶのがベスト
✔ 最大16TBまで増設可能なので、大容量ストレージを構築できる
📌 使えないSSDの例(要注意)
❌ SATA接続のM.2 SSDは使えない(例:Crucial MX500 M.2 SATA)
❌ 企業向けのU.2 / U.3 SSDは非対応(例:Intel Optane SSD P4800X)
❌ PCIe 5.0の超高速SSDはオーバースペック(例:Samsung 990 Pro)
💡 まとめ:SSD選びのポイント
✅ M.2 2280(PCIe 3.0 x2)対応ならOK
✅ SATAのM.2 SSDは使えないので要注意
✅ NAS用途なら「耐久性重視」、一般用途なら「コスパ重視」のSSDを選ぼう
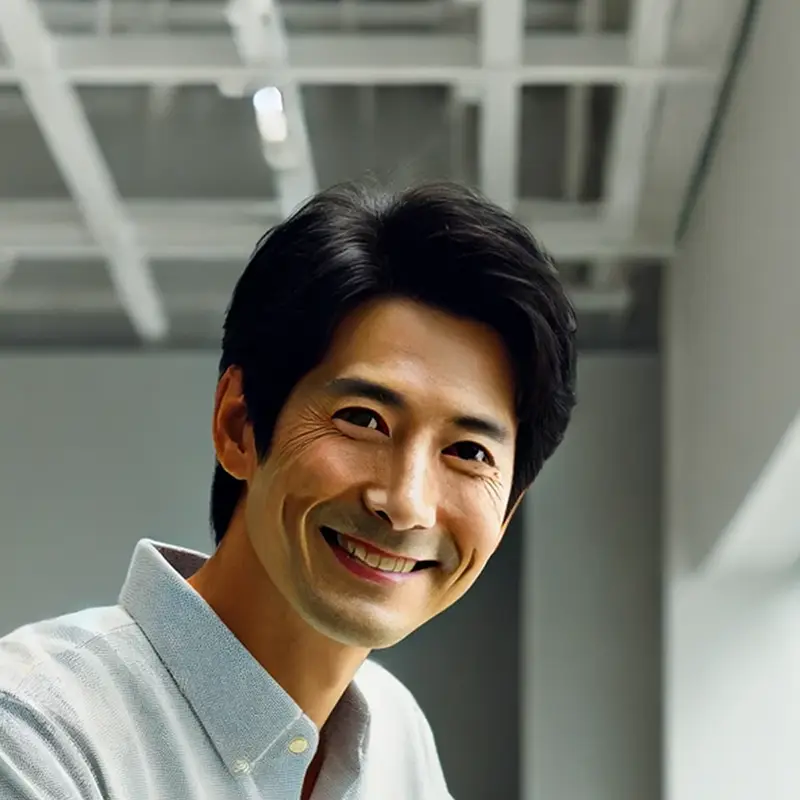
NAS専用機でも同じことですが、NASとして利用するのであれば、保存媒体(SSDやHDD)は信頼性の高い製品(当然価格も上がるが)を選ぶのが鉄板です。
Q4. どんなOSが動作する?Windows以外も使える?
A. GMKtec G9は「Windows 11 Pro」と「Ubuntu」がプリインストール済み。Linux系OSもインストール可能です。
📌 GMKtec G9のOSサポート状況
- プリインストール済み:Windows 11 Pro & Ubuntu(デュアルブート対応)
- 公式対応:Windows 11 / Windows 10 / Ubuntu
- ユーザー導入実績あり:TrueNAS / OpenMediaVault / Proxmox / Debian
📌 OSの選び方(用途別)
✅ Windows 11 Pro(標準OS)
✔ 一般的なPC作業(Office・ブラウジング・動画視聴)
✔ NAS機能も使える(Windowsのファイル共有機能)
✔ 初心者でも扱いやすい
✅ Ubuntu(Linux系OS)
✔ NAS用途(Samba / NFS / FTPサーバー)
✔ 開発環境(Docker / Webサーバー / Python)
✔ 軽量で省メモリなので、リソースを抑えられる
✅ TrueNAS / OpenMediaVault(NAS専用OS)
✔ 本格的なNAS運用(RAID / ZFS / データバックアップ)
✔ 高機能なファイル共有サーバーを構築できる
✔ WindowsやLinuxと比べて、NAS向けに最適化されている
✅ Proxmox VE(仮想化OS)
✔ 仮想マシン(VM)を複数立ち上げたい人向け
✔ 1台のPCでWindows / Linuxを並行して運用可能
📌 公式対応外のOSも動作可能
GMKtec G9は「x86(Intel)」アーキテクチャなので、基本的に多くのOSをインストールできる。
ただし、ドライバーの互換性や動作確認は事前にチェックが必要になります。
❌ MacOS(Hackintosh)は非対応(動作報告なし&互換性の問題あり)。
❌ Android-x86系OS(PrimeOS, BlissOS)は一部機能が制限される可能性あり。
💡 まとめ:OS選びのポイント
✅ Windows 11 Pro / Ubuntuがプリインストール済みですぐに使える
✅ Linux系やNAS専用OSも導入可能(TrueNAS / OpenMediaVault など)
✅ 仮想化したいならProxmoxもアリ
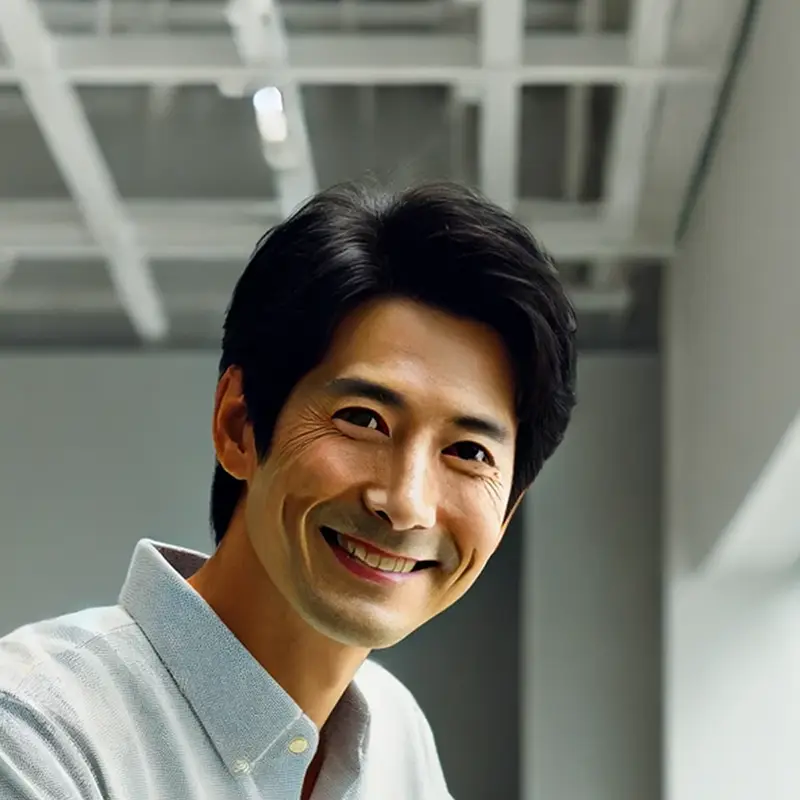
Synology などNAS専用機は専用OSが稼働するので自由度はない。高価なので専用機はちょっと…、という方は、G9を利用するのは一つの解決手段かもしれない。
▼本体だけ(HDDなし)でこのお値段。
Q5. BIOSで設定できる項目は?ブート順や電源管理の変更は可能?
A. はい。GMKtec G9のBIOSでは、ブート順の変更や電源管理、メモリ設定などの基本的な調整が可能です。
📌 GMKtec G9のBIOSの特徴
- UEFI BIOS搭載(マウス操作可能なGUI)
- ブート順変更・Wake on LAN(WoL)・電源管理が可能
- 一部の詳細設定(CPUオーバークロックなど)は制限あり
📌 設定できる主要な項目
✅ ブート関連(OS選択・起動順)
- ブートデバイスの優先順位変更(SSD・USB・ネットワークブート)
- Secure Boot(セキュアブート)の有効/無効
- Fast Boot(高速起動)の有効/無効
✅ 電源管理(NAS用途向け)
- Wake on LAN(WoL) → ネットワーク経由でPCを起動できる(NAS運用に便利)
- Power on after AC loss(停電復帰時の動作) → 電源復帰後に自動で起動する設定
- S3/S4/S5パワーステート制御 → スリープ・休止状態の動作設定
✅ パフォーマンス設定
- メモリ設定(XMP対応なし、基本クロック調整のみ)
- CPU電力管理(TDP設定・パフォーマンスモード調整)
✅ 周辺機器・接続設定
- USBの有効/無効(セキュリティ対策として特定のUSBを無効化可能)
- 内蔵Wi-Fi / Bluetoothのオン・オフ
- PCIeスロットの動作モード
📌 設定時の注意点
❌ オーバークロック関連の詳細設定は不可(N100は固定クロック)
❌ 一部のBIOS設定を誤ると起動できなくなる可能性あり(変更前にメモを取ると安心)
✅ ブート順や電源管理は簡単に変更可能。NAS用途にも便利
💡 まとめ:BIOSでできること
✅ ブート順変更&セキュアブートの設定OK
✅ Wake on LAN・電源管理もカスタマイズ可能(NAS向けに便利)
✅ オーバークロックやXMP設定は不可(CPU/メモリの制限あり)
購入・セットアップ
Q6. GMKtec G9にはどんな付属品がある?
A. GMKtec G9の付属品は、すぐにセットアップできるように必要なものが揃っています。
📌 GMKtec G9の同梱品一覧
- 本体(GMKtec G9 ミニPC)
- 65W ACアダプター(電源ケーブル付き)
- VESAマウントキット(ネジ付き)
- HDMIケーブル(約1m)
- 取扱説明書 & 保証書
✅ 付属品のポイント
✔ ACアダプター付き → すぐに使える(別途購入不要)
✔ VESAマウント対応 → モニター裏に取り付け可能で省スペース化できる
✔ HDMIケーブル同梱 → すぐにディスプレイと接続できる
❌ キーボード・マウスは別売り → 必要なら別途準備しよう
💡 まとめ:
必要なものは一通り揃っているが、キーボードやマウスは別途用意しよう
Q7. 初回セットアップにかかる時間は?初心者でも簡単?
A. セットアップはシンプル。Windowsなら約15~20分、Ubuntuならさらに短時間で完了。
📌 GMKtec G9の初回セットアップの流れ(Windows 11 Pro)
- 電源とHDMIケーブルを接続し、電源ボタンを押す
- Windows 11の初回設定(言語・Wi-Fi・Microsoftアカウント登録)
- セットアップ完了後、Windows Updateを実行(10分~15分)
- 必要なソフトウェア(ブラウザ・オフィス系アプリなど)をインストール
📌 初回セットアップ時間の目安
- Windows 11 Pro → 約15~20分(アップデート込み)
- Ubuntu → 約5~10分(セットアップがシンプル)
📌 初心者でも簡単?
✅ Windows 11はガイドに従うだけなので、初心者でもOK
✅ Ubuntuは最初からインストールされているので、すぐに使える
✅ NAS用途なら、UbuntuでSambaやNFSを設定すればすぐにファイル共有可能
❌ デュアルブートの設定を変更したい場合は、BIOS設定が必要(少し知識が必要)
💡 まとめ:GMKtec G9のセットアップは簡単、初心者でも問題なし
✅ Windowsの初回セットアップは約15~20分
✅ Ubuntuなら5~10分で即スタート可能
✅ NAS用途でも、Ubuntuベースならすぐに運用開始OK
Q8. WindowsとUbuntu、どっちを選ぶべき?デュアルブートの切り替え方法は?
A. GMKtec G9はWindows 11 Pro & Ubuntuのデュアルブート対応、用途に合わせて選べる。
📌 WindowsとUbuntu、どっちが向いている?
| 用途 | Windows 11 Pro | Ubuntu(Linux) |
|---|---|---|
| 初心者向けの使いやすさ | ◎(直感的・GUIが豊富) | △(Linux経験があればOK) |
| 一般的なPC作業(ブラウジング・Office) | ◎ | △(LibreOfficeなど代替ソフトが必要) |
| NAS用途(ファイルサーバー・Samba) | ◯(簡単なファイル共有ならOK) | ◎(本格的なNAS運用向け) |
| 開発・プログラミング | △(Windows Subsystem for Linuxで対応可) | ◎(Linux環境がそのまま使える) |
| 軽量・省メモリ運用 | △(バックグラウンドプロセス多め) | ◎(軽量でリソース効率が良い) |
✅ Windows 11 Proが向いている人
✔ 一般的なPCとして使いたい(Office・ブラウジングなど)
✔ 初心者でLinuxに慣れていない
✔ Windows専用のアプリ(Adobe系・ゲームなど)を使う予定
✅ Ubuntuが向いている人
✔ NAS運用・Linuxサーバーとして使いたい
✔ 開発環境(Docker・Python・Webサーバー)を構築したい
✔ できるだけ軽く運用して、メモリやCPUを効率よく使いたい
📌 デュアルブートの切り替え方法
GMKtec G9は、電源ON時に「ブートメニュー(BIOS)」を開くことで、WindowsとUbuntuを切り替え可能
📌 切り替え手順(Windows ⇄ Ubuntu)
- PCを再起動し、「F7キー」を連打(BIOSのブートメニューを開く)
- 「Boot Manager」画面で、起動したいOSを選択
- 選択後、EnterキーでOSを起動
✅ 頻繁にOSを切り替えるなら、GRUBブートローダーの設定を変更すると便利
✅ Windowsの高速スタートアップを無効化すると、ブート選択がしやすくなる
💡 まとめ:WindowsとUbuntu、どっちを選ぶ?
✅ 初心者&一般的なPC用途 → Windows 11 Pro
✅ NAS運用&開発向け → Ubuntuが最適
✅ デュアルブート対応なので、用途に応じて切り替えも可能
Q9. NASとして使う場合、最適なSSDの容量は?
A. 用途に応じて500GB〜4TBが目安。基本的なファイル共有なら1TB、動画・バックアップ用途なら2TB以上がオススメ。
📌 用途別の最適なSSD容量(選び方ガイド)
| 用途 | 推奨容量 | ポイント |
|---|---|---|
| 基本的なファイル共有(ドキュメント・写真) | 500GB〜1TB | 少量のデータなら十分。低コストで運用可能 |
| 動画・音楽のストリーミング(Plex・DLNA) | 1TB〜2TB | 高画質動画を扱うなら最低1TB以上 |
| PCのバックアップ(定期保存) | 2TB〜4TB | 長期保存するなら大容量モデルが安心 |
| 仮想マシン・Docker運用 | 1TB以上 | コンテナやVMを使うなら余裕をもった容量確保 |
| RAID構成(冗長性重視) | 2TB×2(RAID1)以上 | データ保護を考えるならRAID1でミラーリング |
✅ メリット
✔ SSDならHDDより静かで高速
✔ 省電力で24時間運用に最適
✔ 耐久性が高く、HDDより長持ち
❌ 注意点
⚠ 容量が大きいほど価格が高い(コスパを考えて選ぼう)
⚠ NAS用途なら耐久性の高い「TBW(総書き込みバイト数)」が多いモデルを
⚠ RAID1を組む場合は、2台のSSDが必要(データ保護のため)
💡 まとめ:NAS用SSDはどれを選ぶ?
✅ 普段使いなら 1TB SSD
✅ 動画やバックアップ用なら 2TB〜4TB
✅ RAID1で安全運用するなら 2TB×2
Q10. ファームウェアやBIOSのアップデート方法は?
A. GMKtec G9のファームウェアやBIOSは、公式サイトからダウンロードしてアップデート可能。
手順に沿って、安全に更新しましょう。
📌 ファームウェア・BIOSのアップデート手順(簡単)
1.GMKtecの公式サイトにアクセス
➡ 公式ダウンロードページ から最新のファームウェア・BIOSを入手
2.ファイルをUSBメモリに保存
➡ USBメモリをFAT32形式でフォーマットし、ダウンロードしたファイルを解凍してコピー
3.PCを再起動し、BIOS画面に入る
➡ 「F7キー」 を連打してBIOS設定にアクセス
4.「Update Firmware」または「BIOS Update」を選択
➡ 画面の指示に従い、USBメモリからアップデートファイルを選択
5.アップデート完了後、自動で再起動
➡ 設定がリセットされる場合があるので、必要ならBIOSを再設定
✅ メリット
✔ 最新のBIOSで安定性向上 & 不具合修正
✔ 新しいハードウェアや機能をサポート
✔ パフォーマンス改善の可能性も
❌ 注意点
⚠ アップデート中に電源を切らない(故障の原因になる)
⚠ 公式サイトの正しいバージョンを選ぶ(モデルに適したファームウェアを)
⚠ アップデート後、初回起動時に設定がリセットされる場合あり(BIOS設定を確認)
💡 まとめ:BIOS・ファームウェアのアップデートが必要な人は?
✅ 最新の機能や安定性向上を求める人
✅ ハードウェアの互換性に問題がある人
✅ メーカー推奨のアップデートがある場合
▼公式サイトのBIOSアップデート方法動画
こちらの記事でも紹介してます。
GMKtec G5のトラブル解決ガイド: よくある問題と対策
GMKtec G5のトラブル解決ガイド!電源が入らない、OSが起動しない、ドライバの不具合、ファームウェア更新など、よくある問題の対策を詳しく解説。初心者も安心のサポート情報でトラブルを素早く解決!
ネットワーク・NAS
Q11. デュアル2.5GbEのメリットは?家庭用LANで活かせる?
A. 2.5GbEは、通常の1GbEより高速で低遅延。特にNASや高解像度ストリーミング、大容量データ転送で威力を発揮します。
📌 デュアル2.5GbEのメリット(何がすごい?)
| 特徴 | 1GbE | 2.5GbE |
|---|---|---|
| 最大速度 | 約1Gbps(125MB/s) | 約2.5Gbps(312MB/s) |
| 動画編集・4K/8K配信 | △(帯域不足の可能性) | ◎(スムーズなデータ転送) |
| NAS・ファイル共有 | ◯(一般用途なら十分) | ◎(大容量データも快適) |
| オンラインゲーム | ◯(安定性重視ならOK) | ◎(低遅延でより快適) |
| 家庭用での活用度 | ◯(標準的) | △(環境次第で活かせる) |
📌 家庭用LANで活かせる?(ポイント解説)
✅ 活かせるケース
✔ NASやPC間で大量のファイル転送をする
✔ PlexやDLNAで高解像度の動画をストリーミング
✔ ゲームやリモートワークで低遅延を求める
❌ 活かせないケース
⚠ ルーターやスイッチが1GbEしか対応していない
⚠ インターネット回線が1Gbps以下(多くの家庭用回線では違いが出にくい)
⚠ 普段の用途がWeb閲覧やメール程度(高速通信の恩恵が少ない)
💡 まとめ:デュアル2.5GbEはどんな人向け?
✅ NAS・大容量データ転送を頻繁に行う人
✅ 高解像度の動画ストリーミングを快適にしたい人
✅ 将来のネットワーク環境アップグレードを考えている人
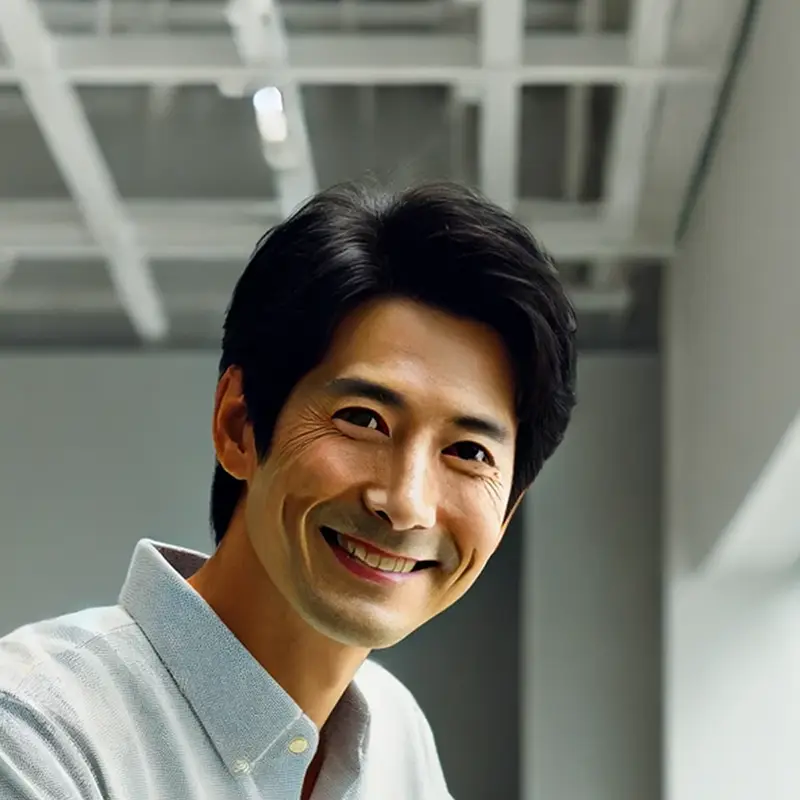
おすすめのハブ、ルーターは、「GMKtec G9 レビュー!NASもOKな高性能ミニPCの実力を徹底検証」にて紹介しています。
Q12. GMKtec G9をNASとして使うにはどう設定すればいい?
A. GMKtec G9をNASとして使うには、OSに応じてファイル共有機能を設定。
Windowsなら「ファイル共有」、Ubuntuなら「Samba」や「NFS」で簡単にNAS化できます。
📌 NASの基本設定(Windows / Ubuntu)
| OS | 設定方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| Windows 11 Pro | 「ファイル共有」機能を有効化 | 簡単設定・Windows同士ならスムーズ |
| Ubuntu | 「Samba」または「NFS」を導入 | Linux & macOSとも相性◎ |
| 専用NAS OS(TrueNAS, OpenMediaVault) | USBブートでインストール | 本格的なNAS運用向け |
📌 Windowsでの設定手順(簡単)
1.共有フォルダを作成
➡ 右クリック → [プロパティ] → [共有] タブで「詳細な共有」有効化
2.ユーザー権限を設定
➡ 「アクセス許可」で特定ユーザーや「Everyone」に権限を付与
3.ネットワーク経由でアクセス
➡ 他のPCで「\[GMKtecのIPアドレス]」にアクセスし、フォルダをマウント
📌 Ubuntu(Linux)での設定手順(Sambaを使う)
1.Sambaをインストール
sudo apt update && sudo apt install samba -y2.共有フォルダを作成 & 設定
sudo mkdir -p /srv/samba/share
sudo chmod 777 /srv/samba/share3.Sambaの設定ファイルを編集
sudo nano /etc/samba/smb.conf➡ 以下を追加:
[SharedFolder]
path = /srv/samba/share
read only = no
browsable = yes
guest ok = yes4.Sambaを再起動し、アクセス確認
sudo systemctl restart smbd➡ Windowsから「\[GMKtecのIPアドレス]\SharedFolder」でアクセス
✅ メリット
✔ 省電力で常時稼働OK(HDD / SSDをNAS化)
✔ デュアル2.5GbEで高速ファイル転送が可能
✔ Windows / Linux どちらの環境でも対応
❌ 注意点
⚠ RAID機能はないため、バックアップ対策を忘れずに
⚠ 常時稼働する場合は冷却対策も考慮(ファン制御を調整)
⚠ リモートアクセスする場合は、VPNやSSH設定を強化
💡 まとめ:GMKtec G9のNAS設定が向いている人は?
✅ ファイル共有を自宅で簡単にしたい
✅ 高性能なミニPCをNASとして活用したい
✅ 専用NAS機器より自由にカスタマイズしたい
Q13. NAS専用OS(TrueNAS・OpenMediaVault)はインストールできる?
A. はい。GMKtec G9にはTrueNASやOpenMediaVaultをインストール可能です。USBメモリからセットアップできます。
📌 インストール手順(共通)
1.公式サイトからTrueNASまたはOpenMediaVaultのISOファイルをダウンロード
2.Rufusなどのツールを使い、USBメモリに書き込む(ブート用USB作成)
3.BIOSでUSBメモリを優先ブートに設定し、OSインストールを開始
➡ GMKtec G9を再起動し、「F7キー」を連打
➡ USBメモリを選択してインストーラーを起動
➡ 空のSSD / HDDを選び、指示に従ってインストール
4.セットアップウィザードに従い、ストレージ・ネットワーク設定を行う
5.インストール後、Web管理画面にアクセスし詳細設定を行う
➡ TrueNAS: 「http://[G9のIPアドレス]」にアクセス
➡ OpenMediaVault: 「http://[G9のIPアドレス]:8080」にアクセス
📌 TrueNASとOpenMediaVaultの違い
✅ TrueNAS(ZFSベースの高機能NAS)
- データ保護に強い(ZFSファイルシステム対応)
- 企業レベルのストレージ管理が可能
- メモリを多く使用する(最低8GB推奨)
✅ OpenMediaVault(軽量で扱いやすいNAS)
- WebUIがシンプルで初心者向け
- 低スペックPCでも動作可能(メモリ2GB以上推奨)
- プラグインで機能拡張が可能
✅ メリット
✔ 専用NAS機器と同等の機能が使える(ZFS, RAID, Docker対応)
✔ デュアル2.5GbEで高速ファイル転送
✔ 柔軟にストレージを拡張可能
❌ 注意点
⚠ システム用のSSDを別途用意するのがオススメ(USBや小容量SSD)
⚠ ZFSを使う場合はメモリ8GB以上推奨(TrueNAS向け)
⚠ 消費電力や発熱に注意(24時間稼働の場合は冷却対策を)
💡 まとめ:NAS専用OSを導入すべき人は?
✅ 本格的なNAS運用をしたい(RAID / ZFS対応)
✅ 家庭用よりも高度なデータ管理が必要
✅ クラウドやDockerアプリを活用したい
Q14. RAID構成は可能?ソフトウェアRAIDの設定方法は?
A. GMKtec G9はソフトウェアRAIDを使用すればRAID構成が可能です。
Windowsなら「ストレージプール」、Linuxなら「mdadm」でRAIDを構築できます。
📌 RAIDの種類と特徴(どれを選ぶ?)
| RAID種類 | 特徴 | 用途 |
|---|---|---|
| RAID 0(ストライピング) | 速度重視・データ保護なし | 高速なストレージが必要な場合 |
| RAID 1(ミラーリング) | データ保護◎・書き込み速度低下 | 大事なデータを守りたい場合 |
| RAID 5(パリティ分散) | 3台以上のディスクで冗長性確保 | バランス型のNAS構成 |
| RAID 10(RAID 1+0) | 高いパフォーマンス&冗長性 | 速度とデータ保護を両立したい場合 |
📌 WindowsでのソフトウェアRAID設定(ストレージプールを使用)
1.ディスクの管理を開く
➡ 「スタート」→「ディスクの管理」を開く
2.ストレージプールを作成
➡ 「ストレージスペースの管理」→「新しいプールとストレージスペースの作成」
3.RAIDレベルを選択
➡ 「ミラー(RAID 1)」または「パリティ(RAID 5相当)」を選択
4.フォーマットして利用開始
➡ NTFSでフォーマットし、ネットワーク共有設定をすればNAS化もOK
📌 Ubuntu(Linux)でのソフトウェアRAID設定(mdadmを使用)
1.mdadmをインストール
sudo apt update && sudo apt install mdadm -y
2.RAIDアレイを作成(例:RAID 1)
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdX /dev/sdY
➡ /dev/sdX と /dev/sdY はRAIDに組み込むディスク
3.RAIDの設定を保存
sudo mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
sudo update-initramfs -u
4.ファイルシステムを作成&マウント
sudo mkfs.ext4 /dev/md0
sudo mount /dev/md0 /mnt/raid
✅ メリット
✔ RAID 1でデータ保護ができる(ミラーリング)
✔ RAID 0なら高速データ転送が可能
✔ ソフトウェアRAIDなので追加機器不要
❌ 注意点
⚠ RAID 0は1台でも故障するとデータ全損(バックアップ必須)
⚠ ソフトウェアRAIDはCPU負荷がかかるため、使用環境によってはパフォーマンスに影響
⚠ RAIDを解除するとデータが消えるため、設定前にバックアップを取る
💡 まとめ:RAID構成が向いている人は?
✅ データの安全性を確保したい(RAID 1)
✅ 高速なストレージを活用したい(RAID 0)
✅ NASやサーバー用途で運用したい(RAID 5 / 10)
Q15. 外付けHDDをNASとして共有できる?USB 3.2接続の速度は?
A. 外付けHDDをNASとして共有できます。
Windowsの「ファイル共有」やUbuntuの「Samba」を使えば、USB接続のHDDもLAN内で共有できます。
📌 外付けHDDをNAS化する方法(Windows / Ubuntu)
| OS | 設定方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| Windows | ファイル共有を有効化 | 簡単・設定が直感的 |
| Ubuntu | Sambaを導入 | Linux・macOSとも相性◎ |
| 専用NAS OS(TrueNAS, OpenMediaVault) | 外付けドライブを追加 | NAS専用機能が利用可能 |
📌 Windowsで外付けHDDをNASとして使う手順(簡単)
1.HDDを接続し、ドライブレターを確認
➡ 例:「E:\」など
2.共有設定を有効化
➡ 「E:\」を右クリック → [プロパティ] → [共有] → 「詳細な共有」
3.アクセス権を設定
➡ 「Everyone」に「読み取り/書き込み」を許可(必要に応じて設定)
4.他のPCからアクセス
➡ 「\[PCのIPアドレス]\E$」でネットワーク共有フォルダに接続
📌 Ubuntuで外付けHDDをNASとして使う方法(Sambaを使用)
1.HDDをマウント
sudo mkdir -p /mnt/exthdd
sudo mount /dev/sdX1 /mnt/exthdd
2.Sambaをインストール
sudo apt update && sudo apt install samba -y
3.Samba設定を編集
sudo nano /etc/samba/smb.conf
➡ 以下を追加
[ExternalHDD]
path = /mnt/exthdd
read only = no
browsable = yes
guest ok = yes
4.Sambaを再起動し、ネットワークからアクセス
sudo systemctl restart smbd
➡ Windowsから「\[GMKtecのIPアドレス]\ExternalHDD」で接続
📌 USB 3.2の速度(どれくらい速い?)
| USB規格 | 最大速度 | 実測(HDDの場合) |
|---|---|---|
| USB 3.0 (3.2 Gen 1) | 5Gbps(約625MB/s) | 約100~150MB/s |
| USB 3.1 (3.2 Gen 2) | 10Gbps(約1250MB/s) | 約300~500MB/s(SSDなら速い) |
| USB 3.2 Gen 2x2 | 20Gbps(約2500MB/s) | 約700~1000MB/s(SSD推奨) |
✅ 外付けHDDは100~150MB/s程度が一般的
✅ SSDならUSB 3.2 Gen 2で500MB/s超えも可能
✅ メリット
✔ 安価にNAS環境を構築できる
✔ USB 3.2対応なら高速転送も可能
✔ 専用NAS機器を買わなくても簡単に共有できる
❌ 注意点
⚠ USB接続は常時接続には向かない(長時間運用で切断のリスクあり)
⚠ RAIDやZFSのようなデータ保護機能がない(バックアップ推奨)
⚠ 低速なUSBポートではNASとしての実用性が低くなる(USB 3.2推奨)
💡 まとめ:外付けHDDをNASとして使うべき人は?
✅ 低コストで簡単にNASを構築したい
✅ 一時的なファイル共有やバックアップ用途
✅ USB 3.2でできるだけ高速な転送を活かしたい
Q16. VPNを設定して外部からアクセスする方法は?(Tailscale・WireGuard)
A. GMKtec G9にVPNを設定すれば、外部ネットワークから安全にアクセスできる。
Tailscaleなら簡単に、WireGuardなら高速&セキュアなVPN環境を構築できます。
📌 VPNの選び方(どっちを使う?)
📌 TailscaleでVPNを設定(簡単)
1.Tailscaleをインストール
➡ 公式サイト からダウンロードし、インストール
2.Tailscaleを有効化
➡ Windowsならアプリを起動、Ubuntuなら以下のコマンドで開始
sudo tailscale up
3.他のデバイスと接続
➡ スマホや別のPCにもTailscaleをインストールし、同じアカウントでログイン
➡ 「Tailscale IPアドレス」を使ってリモートアクセス可能
✅ メリット
✔ 設定が簡単で即使える
✔ NAT越えが不要でどこでも接続可能
❌ 注意点
⚠ クラウド経由のため、プライバシーが気になる場合は WireGuard 推奨
📌 WireGuardでVPNを設定(高速&セキュア)
1.WireGuardをインストール
➡ Windows: 公式サイト からダウンロード
➡ Ubuntu:
sudo apt update && sudo apt install wireguard -y
2.VPNサーバーの設定
➡ wg0.conf を作成し、以下のように設定
[Interface]
Address = 10.0.0.1/24
PrivateKey = (サーバーの秘密鍵)
ListenPort = 51820
[Peer]
PublicKey = (クライアントの公開鍵)
AllowedIPs = 10.0.0.2/32
3.WireGuardを起動
sudo wg-quick up wg0
4.クライアント側で接続
➡ スマホやPCにWireGuardをインストールし、QRコードまたは設定を追加
✅ メリット
✔ 高速で安定したVPN通信
✔ 直接P2P接続が可能でプライバシー◎
❌ 注意点
⚠ ポート開放(51820/UDP)が必要(ルーターで設定)
⚠ 設定が少し複雑(コマンド操作が必要)
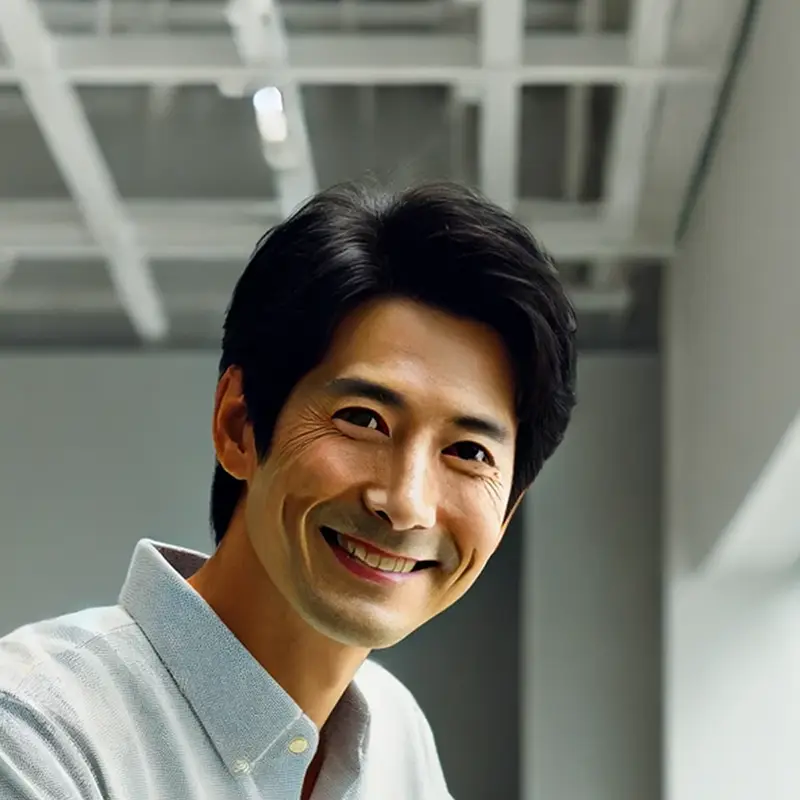
このあたりはセキュリティのこともあるので、十分な知識がないと手を出しにくいところですね。
冷却・静音性・消費電力
Q17. 24時間稼働させても大丈夫?電源管理の設定は?
A. GMKtec G9は24時間稼働も大丈夫です。
ただし、発熱対策や電源管理を適切に設定することで安定運用が可能になります。
📌 24時間稼働のポイント(何に気をつける?)
| 項目 | 推奨設定・対策 | 理由 |
|---|---|---|
| 冷却対策 | ファン制御ソフト・冷却パッド使用 | 長時間稼働で発熱を抑える |
| 電源管理 | 「スリープ無効」&「自動再起動設定」 | 安定稼働&トラブル時の復旧 |
| SSD/HDD管理 | 「電源オプション」でディスク休止設定 | 不要な消耗を防ぐ |
| BIOS設定 | 「Power on AC Loss: ON」 | 停電後の自動復帰 |
📌 Windowsでの電源管理設定(簡単)
1.電源オプションを開く
➡ 「設定」→「システム」→「電源とスリープ」→「追加の電源設定」
2.スリープを無効化
➡ 「コンピューターがきどうスリープ状態になる時間」を「なし」に設定
3.ディスクの省電力設定を調整
➡ 「ハードディスクの電源を切る」→ 30分~60分に設定
4.自動再起動を有効化
➡ 「システムのプロパティ」→「起動と回復」→「自動的に再起動する」にチェック
📌 Ubuntu(Linux)での電源管理設定
1.スリープ&自動シャットダウンを無効化
sudo systemctl mask sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target
2.HDDの省電力設定を調整(30分後に休止)
sudo hdparm -S 60 /dev/sdX
3.停電後の自動起動(BIOS設定)
➡ BIOSで「Power on AC Loss」を ON に設定
✅ メリット
✔ 省電力設定で長時間稼働でも負荷を抑えられる
✔ 停電後も自動で復旧できる設定が可能
✔ 発熱対策をすれば安定運用できる
❌ 注意
⚠ ファン制御を適切にしないと熱暴走のリスクあり(BIOS or ソフトで設定)
⚠ SSD / HDDの寿命を考慮し、バックアップ対策を忘れずに
⚠ UPS(無停電電源装置)を使うとさらに安全(停電対策)
💡 まとめ:24時間稼働させるなら?
✅ 冷却対策をしっかり(冷却パッド or ファン制御)
✅ スリープ&自動電源管理を調整
✅ 停電対策で「Power on AC Loss」をON
Q18. 静音性はどのくらい?ファンの音は気になる?
A. GMKtec G9は比較的静音ですが、負荷がかかるとファンの音が気になる場合あり
アイドル時は約25dB、負荷時は最大40dB前後。冷却設定を最適化すればさらに静かにできます。
📌 GMKtec G9の静音性チェック(どのくらい静か?)
| 動作状態 | ファンノイズ(目安) | 体感レベル |
|---|---|---|
| アイドル時(待機) | 約25dB | ほぼ無音(静かな部屋でも気にならない) |
| 軽作業(ブラウジング・動画再生) | 約30dB | ささやき声程度の静かさ |
| 高負荷(ゲーム・動画編集) | 約40dB | 一般的なノートPC並みのファン音 |
| 最大負荷(ベンチマーク・長時間稼働) | 約45dB | やや気になるが、一般的なデスクトップPCよりは静か |
📌 ファンの音を抑える方法(簡単)
✅ BIOSでファンの回転数を調整
➡ 「Fan Mode」を「Silent」に変更すると、低回転で静音化可能
✅ Windowsなら「ファン制御ソフト」を活用
➡ 「SpeedFan」や「Fan Control」で回転数をカスタマイズ
✅ 高負荷時の発熱を抑える工夫
✔ 排熱スペースを確保(壁や物を近づけない)
✔ 冷却パッドや静音ファンを活用(放熱効果UP)
✔ 電源プランを「省電力モード」に(発熱を抑える)
✅ メリット
✔ アイドル時はほぼ無音で快適
✔ 高負荷時でも一般的なノートPCよりは静か
✔ 冷却設定を最適化すれば、さらに静音化可能
❌ 注意点
⚠ 完全な無音ではない(特に高負荷時)
⚠ 冷却性能を落としすぎると、熱暴走のリスクあり
⚠ 長時間高負荷作業をすると、ファン音が気になりやすい
💡 まとめ:GMKtec G9の静音性は?
✅ 軽作業ならほぼ無音で快適
✅ 高負荷時はややファン音が出るが、設定次第で静かにできる
✅ 冷却対策をすれば、より静か&安定運用が可能
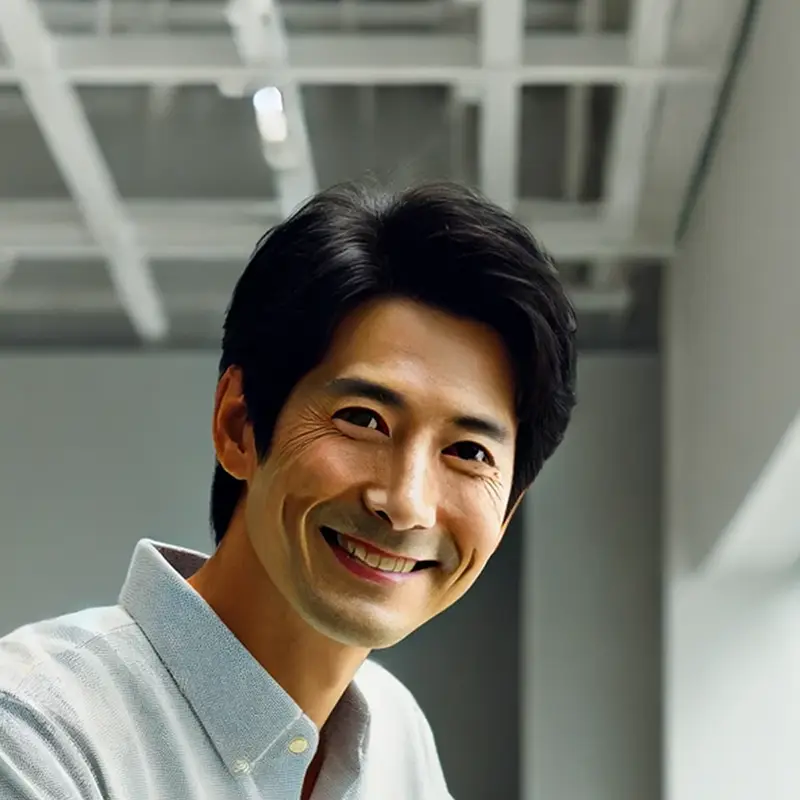
G5 と違い、G9 は分解しやすい構造になっている。放熱性の高いパーツを使っているので、発熱が心配な方も大丈夫。(G9レビュー記事参照)
Q19. 発熱はどの程度?冷却ファンやヒートシンクを追加するべき?
A. GMKtec G9は通常使用では適切に冷却されるが、高負荷時には発熱が増加
CPU温度はアイドル時約40℃、負荷時最大85℃前後。追加冷却で安定運用が可能です。
📌 GMKtec G9の温度目安(どれくらい熱くなる?)
| 動作状態 | CPU温度 | 体感温度(本体) |
|---|---|---|
| アイドル時(待機) | 約35〜45℃ | ほんのり暖かい |
| 軽作業(ブラウジング・動画視聴) | 約50〜65℃ | 少し熱を感じる程度 |
| 高負荷(ゲーム・エンコード) | 約75〜85℃ | 明らかに熱い(長時間使用で注意) |
| 最大負荷(ベンチマーク・OC時) | 約85〜90℃ | 手で触ると熱いレベル(追加冷却推奨) |
📌 冷却対策(温度を下げる方法)
✅ BIOSでファン設定を変更
➡ 「Fan Mode」を「Performance」にすると冷却性能UP(ただしファン音は大きくなる)
✅ 冷却ファンやヒートシンクの追加
✔ ノートPC用冷却パッドを使用(放熱効果◎)
✔ USB接続の外付けファンでエアフロー強化
✔ M.2 SSD用のヒートシンクを追加(SSD温度を下げる)
✅ 放熱を妨げない設置方法
✔ PCを壁や狭いスペースに置かない(エアフロー確保)
✔ 底面のゴム足を追加し、空間を作る(放熱効果UP)
✅ メリット
✔ 追加冷却で長時間稼働も安心
✔ パフォーマンスの低下を防ぎ、安定動作
✔ SSDの温度も下げられ、寿命を延ばせる
❌ 注意点
⚠ 高負荷時はファン音が大きくなる可能性あり
⚠ 設置場所によっては熱がこもりやすい(こまめに温度チェック推奨)
⚠ 冷却パッドや外付けファンはコストがかかる(必要に応じて追加)
💡 まとめ:追加冷却が必要な人は?
✅ 高負荷作業(ゲーム・動画編集・エンコード)をする
✅ 24時間運用で安定性を求める
✅ 温度が高くなると気になる or ファン音を抑えたい
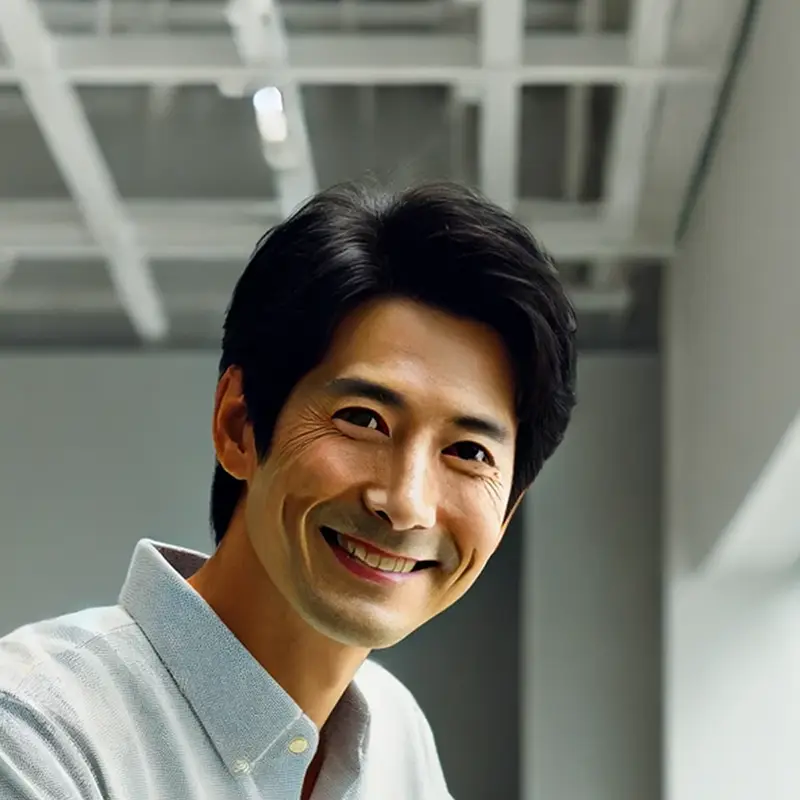
結局は熱対策が必要になる。特に夏場はどうするか。エアコンない部屋だと温風しか回らないので、なんらかの対策が必要です。NASとして利用するなら、ヒートシンクをつけましょう!
Q20. 省電力モードやスリープ運用は可能?電気代はどのくらい?
A. GMKtec G9は省電力モードやスリープ運用が可能
アイドル時の消費電力は約10W、高負荷時でも最大35W程度なので、電気代を抑えながら24時間稼働もOK
📌 消費電力の目安(どれくらい電気を使う?)
| 動作状態 | 消費電力(目安) | 電気代(月額)※24時間稼働 |
|---|---|---|
| スリープ時 | 約2〜3W | 約50円 |
| アイドル時(待機) | 約8〜12W | 約250円 |
| 軽作業(ブラウジング・動画再生) | 約15〜20W | 約450円 |
| 高負荷(ゲーム・動画編集) | 約30〜35W | 約750円 |
✅ 24時間稼働しても月額1,000円以下(一般的なデスクトップPCより省電力)
📌 省電力モードやスリープ運用の設定(Windows / Ubuntu)
✅ Windowsで省電力設定をする方法
1.電源オプションを開く
➡ 「設定」→「システム」→「電源とスリープ」
2.スリープ時間を設定
➡ 「ディスプレイの電源を切る」→ 5分〜15分
➡ 「PCをスリープ状態にする」→ 30分〜1時間(必要に応じて調整)
3.USBやネットワークのスリープ解除を有効化
➡ 「デバイスマネージャー」→「ネットワークアダプター」→「電源の管理」で「このデバイスでスリープ解除を許可する」をON
✅ Ubuntu(Linux)で省電力設定をする方法
1.スリープを有効化
sudo systemctl unmask sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target
2. 一定時間後にスリープする設定
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power sleep-inactive-ac-timeout 1800
➡ 1800秒(30分)後にスリープ
3.Wake-on-LAN(WOL)を有効化(リモートから復帰可能)
sudo ethtool -s eth0 wol g
✅ メリット
✔ 省電力で長時間稼働も安心
✔ スリープ運用で消費電力を最小限に抑えられる
✔ WOLを設定すれば、リモートから復帰も可能
❌ 注意点
⚠ スリープ中は一部のネットワーク機能が停止する可能性あり
⚠ 省電力モードによってはパフォーマンスが落ちることも(必要に応じて調整)
⚠ Wake-on-LANを使う場合は対応ルーターが必要
💡 まとめ:省電力運用が向いている人は?
✅ 常時稼働させつつ、できるだけ電気代を抑えたい
✅ スリープを活用して、使わない時間の消費電力を減らしたい
✅ リモートからWake-on-LANで復帰できるようにしたい
Q21. UPS(無停電電源装置)は必要?停電時のリスクは?
A. GMKtec G9を24時間稼働させるならUPS(無停電電源装置)の導入を推奨します。
突然の停電によるデータ損失やシステム障害を防ぎ、安全にシャットダウンできます。
📌 UPSを導入するメリット(なぜ必要?)
✅ 停電時も電源を維持できる(安全にシャットダウン可能)
✅ 電圧の変動や瞬断からPCを保護(ハードウェアの寿命延長)
✅ データの破損やRAID崩壊を防ぐ(特にNAS運用では重要)
📌 UPSなしの場合のリスク(何が起こる?)
| リスク | 影響 |
|---|---|
| 突然のシャットダウン | ファイルやOSが破損する可能性あり |
| NASのRAID崩壊 | 書き込み中のデータが壊れることも |
| SSD/HDDの寿命短縮 | 突然の電源断が繰り返されると影響大 |
| リモートアクセスの中断 | 外部からのVPN接続が突然切れる |
📌 UPSの選び方(どれを選ぶ?)
| 用途 | 推奨UPS容量 | バッテリー持続時間(目安) |
|---|---|---|
| GMKtec G9のみ | 300VA~500VA | 約15~30分 |
| NASやルーターも接続 | 600VA~1000VA | 約30~60分 |
| 複数PC・サーバー運用 | 1000VA以上 | 1時間以上 |
💡 GMKtec G9は消費電力が低いため、小型UPS(300VA程度)でも十分
📌 UPSの基本設定(APC / CyberPowerの場合)
1.UPSを設置し、PCと接続
➡ PCのコンセントをUPSに差し込み、USBケーブルを接続
2.管理ソフトをインストール(自動シャットダウン設定)
💡 愛用しているオススメのUPS
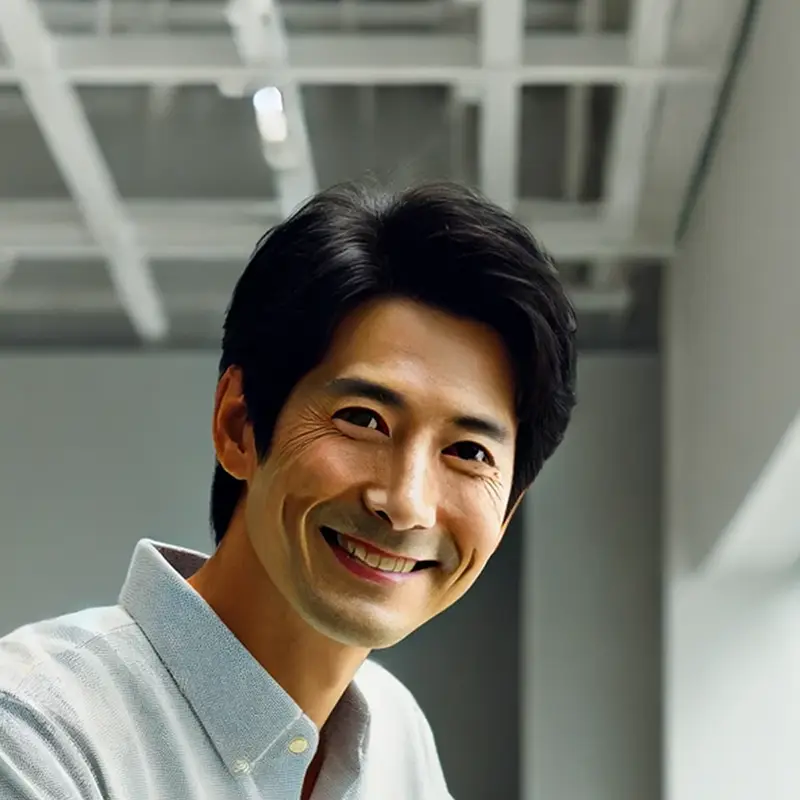
UPSは高価だけどメチャ大事。SSDになってHDD破損のリスクが減ったとはいえ、書き込み中のものの消失・データ破損は避けられない。できれば、PC+ディスプレイ+ルーター+ONU+NAS、これくらいはカバーできる容量が良いです。1〜2分あれば安全にシャットダウンできますからね。このUPSは、バッテリー交換も簡単にできるので長く使える1品です。
使い方・拡張性
Q22. ゲームはできる?どのくらいのタイトルが動く?
A. GMKtec G9は軽量~中程度のゲームなら快適に動作
内蔵GPU(Intel UHD/Intel Iris Xe)搭載なので、設定次第で多くのタイトルがプレイ可能。
📌 GMKtec G9のゲーム性能(どんなゲームが動く?)
| ゲームジャンル | 代表タイトル | 動作の目安 |
|---|---|---|
| 軽量ゲーム(2D / レトロ) | マインクラフト(Java版)、Terraria、Stardew Valley | ◎ 快適(60FPS以上) |
| eスポーツ系 | Valorant、CS:GO、League of Legends、Dota 2 | ◯ 中設定でプレイ可能(40-60FPS) |
| 軽量FPS / TPS | Fortnite、PUBG Lite、Apex Legends(低設定) | △ 低設定なら動作(30-50FPS) |
| オープンワールド / AAA | GTA V、The Witcher 3、Cyberpunk 2077 | × 基本的に厳しい(低FPS) |
| クラウドゲーム | GeForce NOW、Xbox Cloud Gaming、Steam Remote Play | ◎ 快適(ネット環境次第) |
💡 「軽量ゲーム&eスポーツタイトルはプレイOK。高負荷なAAAタイトルは厳しい」
📌 ゲームを快適にする設定(パフォーマンスを上げる)
✅ ゲーム内の設定を最適化
✔ 解像度をフルHD(1920×1080)以下に下げる
✔ グラフィック設定を「低」または「中」に変更
✔ V-SyncをOFFにし、FPS上限を設定(60FPS推奨)
✅ Windowsのパフォーマンスを調整
✔ 「電源プラン」を「高パフォーマンス」に変更
✔ 不要なバックグラウンドアプリを終了(タスクマネージャーで管理)
✔ 最新のIntel GPUドライバーをインストール
✅ 冷却を強化して安定動作
✔ 冷却パッドや外付けファンで温度管理
✔ PCの通気口を塞がないように設置
✅ メリット
✔ 軽量ゲームやクラウドゲームなら快適
✔ eスポーツタイトルは設定次第で十分プレイ可能
✔ 消費電力が低く、省エネでプレイできる
❌ 注意点
⚠ AAAタイトルや最新の3Dゲームは厳しい(GPU性能がボトルネック)
⚠ 冷却対策をしないと高負荷時にパフォーマンス低下の可能性あり
⚠ メモリ8GB以上推奨(ゲームによっては16GBに増設すると安定)
💡 まとめ:どんな人に向いている?
✅ マイクラやLoLなど軽量ゲームをプレイしたい
✅ クラウドゲーム(GeForce NOW / Xbox Cloud)で遊びたい
✅ eスポーツ系タイトルを低設定でプレイしたい
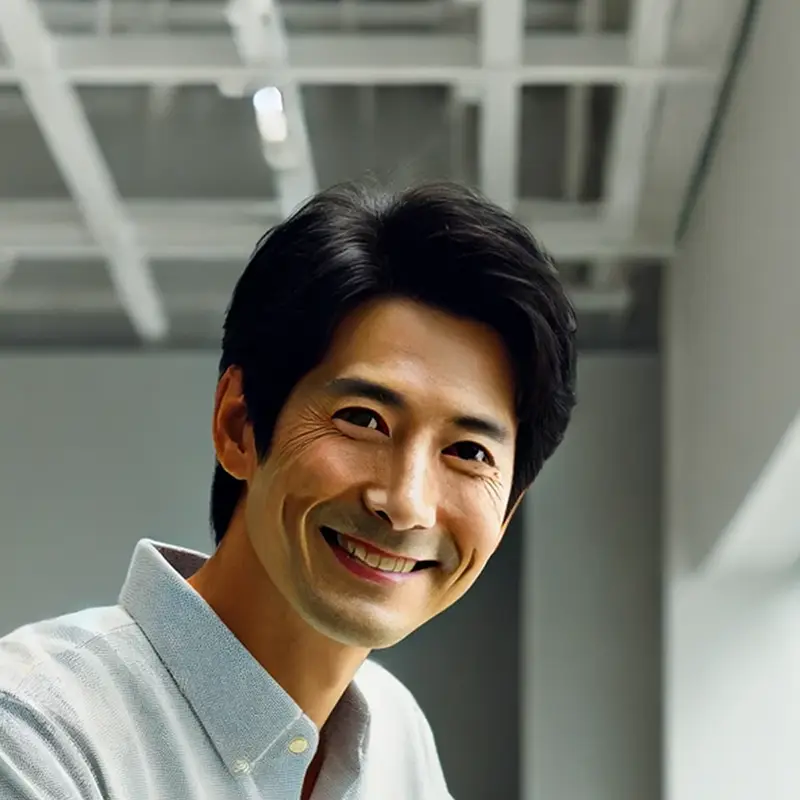
G5 のレビューでも紹介したのですが、囲碁AIなどを快適に利用するにはもっとスペックがほしいところ。
Q23. HDMI出力は4K対応?リフレッシュレートは?
A. GMKtec G9は4K出力対応です。
HDMIとUSB-C(DisplayPort Alt Mode)で最大4K 60Hzの映像出力が可能。
📌 映像出力スペック(どの解像度・リフレッシュレートが使える?)
| 出力ポート | 最大解像度 & リフレッシュレート | 対応規格 |
|---|---|---|
| HDMI 2.0 | 4K @ 60Hz / 1080p @ 120Hz | HDMI 2.0 |
| USB-C(DP Alt Mode) | 4K @ 60Hz / 1080p @ 144Hz | DisplayPort 1.2以上 |
| デュアルディスプレイ | 4K + 4K(60Hz) | HDMI + USB-C併用 |
💡 「4K 60Hzでの出力OK。フルHDなら120Hz以上も可能」
📌 高リフレッシュレートの設定方法(60Hz以上で使うには?)
✅ Windowsでリフレッシュレートを変更
1.「設定」→「システム」→「ディスプレイ」を開く
2.「ディスプレイの詳細設定」をクリック
3.「リフレッシュレート」を60Hzまたは120Hzに設定
✅ 対応ケーブルを使う
✔ 4K 60HzにはHDMI 2.0 / DisplayPort 1.2以上のケーブルが必要
✔ 安価なHDMI 1.4ケーブルでは4K 30Hzまでしか出ないことも
✅ モニターの設定も確認
✔ モニター側の入力設定を「HDMI 2.0」や「DisplayPort」に変更
✔ 一部のモニターはデフォルトで60Hz以上を無効化しているため、手動で調整
✅ メリット
✔ 4K 60Hzの出力が可能で映像がなめらか
✔ デュアルディスプレイ対応で作業効率UP
✔ フルHDなら高リフレッシュレート(120Hz以上)もOK
❌ 注意点
⚠ 古いHDMIケーブルだと4K 30Hzまでしか出ない(HDMI 2.0以上推奨)
⚠ 一部のモニターは設定変更しないと60Hzが有効にならない
⚠ USB-C経由の映像出力は対応モニターが必要(DP Alt Mode対応)
💡 まとめ:GMKtec G9のHDMI出力は?
✅ 4K 60Hz対応で高解像度の映像が楽しめる
✅ フルHDなら120Hz以上の滑らかな表示も可能
✅ デュアルディスプレイもOKで作業環境を拡張できる
Q24. USBポートの最大転送速度は?外付けSSDの速度は?
A. GMKtec G9のUSBポートは最大10Gbps(USB 3.2 Gen 2)対応
外付けSSDを使用すれば、理論上1,000MB/s以上の転送速度が可能。
📌 USBポートの最大転送速度(どのポートが速い?)
| ポート種類 | 最大速度(理論値) | 実測(SSD使用時の目安) |
|---|---|---|
| USB 3.2 Gen 2 (Type-A / Type-C) | 10Gbps(1250MB/s) | 700~1000MB/s |
| USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 5Gbps(625MB/s) | 400~550MB/s |
| USB 2.0 (Type-A) | 480Mbps(60MB/s) | 30~40MB/s |
💡 「USB 3.2 Gen 2(10Gbps)なら外付けSSDの高速転送が可能」
📌 外付けSSDの速度目安(どのSSDが速い?)
| SSDタイプ | 接続方式 | 実測転送速度(目安) |
|---|---|---|
| SATA SSD(外付けケース) | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 400~550MB/s |
| NVMe SSD(USB-C接続) | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 700~1000MB/s |
| NVMe SSD(Thunderbolt 3) | Thunderbolt 3 (40Gbps) | 2000MB/s以上 |
💡 「高速なNVMe SSDならUSB 3.2 Gen 2で1,000MB/s近く出る」
📌 USB 3.2で高速転送するためのポイント
✅ USB 3.2 Gen 2対応のポートを使用
✔ GMKtec G9のUSB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応ポートに接続
✅ 適切なケーブルを使用
✔ USB 3.2 Gen 2対応ケーブル(古いケーブルは速度制限の可能性あり)
✅ SSDのフォーマットを最適化
✔ NTFS / exFATでフォーマット(FAT32は4GB制限あり)
✔ Trim機能を有効化すると長期的な速度低下を防げる
✅ メリット
✔ USB 3.2 Gen 2なら高速転送で作業効率UP
✔ 外付けSSDなら1,000MB/s近い速度でデータ移動が可能
✔ 高速ストレージを活かせば動画編集やゲームのロード時間短縮も
❌ 注意点
⚠ USB 2.0ポートに接続すると速度が大幅に低下(30MB/s程度)
⚠ USB 3.2 Gen 1(5Gbps)では最大500MB/s程度に制限される
⚠ 外付けケースの性能が低いとSSDの本来の速度が出ない
💡 まとめ:GMKtec G9のUSB転送速度は?
✅ USB 3.2 Gen 2なら最大10Gbps(実測700~1000MB/s)
✅ NVMe SSDなら外付けでも超高速転送が可能
✅ ケーブル・ポート・SSDの性能を活かせば、最適なスピードでデータ移動できる
Q25. GMKtec G9をホームシアターPC(HTPC)として使える?
A. GMKtec G9はホームシアターPC(HTPC)として利用可能
4K 60Hz出力、HDR対応、静音設計なので、高画質な映画鑑賞やストリーミングに最適。
📌 HTPCとしての性能(どんな環境で使える?)
| 機能 | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 4K 60Hz出力 | ◎ 対応 | HDMI 2.0 & USB-C (DP Alt Mode) |
| HDR(ハイダイナミックレンジ) | ◯ 一部対応 | WindowsのHDR設定が必要 |
| Dolby Atmos / DTS-X | ◯ 対応(ソフト次第) | HDMIでAVアンプに接続推奨 |
| ストリーミングサービス | ◎ 快適 | Netflix / Amazon Prime / YouTube 4K対応 |
| 静音性 | ◯ 高負荷時は少しファン音あり | 冷却設定を調整するとさらに静音化可能 |
💡 「4K映画、ストリーミング、ローカルメディア再生に最適」
📌 HTPCとしてのセットアップ方法(快適なホームシアター環境を作る)
✅ ディスプレイ設定を最適化
✔ 「設定」→「ディスプレイ」→「HDRを有効化」
✔ 解像度を「3840×2160(4K)」&リフレッシュレートを「60Hz」に設定
✅ メディア再生ソフトを導入
✔ VLCメディアプレイヤー(万能&軽量)
✔ Kodi(本格的なHTPC向けメディアセンター)
✔ MPC-HC + madVR(高画質再生に最適)
✅ 音声出力を強化
✔ HDMI経由でAVアンプに接続し、Dolby Atmos / DTS-Xに対応
✔ USB DACやBluetoothスピーカーと連携して高音質化
✅ ストリーミングサービスを活用
✔ Netflix / Amazon Prime Video / Disney+ / YouTubeの4Kコンテンツを再生
✔ ブラウザで再生時は「ハードウェアアクセラレーション」を有効化
✅ メリット
✔ 4K 60Hz&HDR対応で高画質映像を楽しめる
✔ ストリーミングやローカルメディアの再生がスムーズ
✔ コンパクトで省電力なのでリビングに設置しやすい
❌ 注意点
⚠ Netflixなどの4K再生はEdgeブラウザ推奨(Chromeは制限あり)
⚠ HDR設定を有効にしないと、正しい色が表示されないことがある
⚠ 高負荷時にファン音が少し気になる場合あり(冷却設定推奨)
💡 まとめ:HTPCとして使うのに向いている?
✅ 4K映画やストリーミングを大画面で楽しみたい
✅ Dolby Atmos / DTS-X対応のAVアンプと接続して高音質で楽しみたい
✅ 省スペース&省電力でリビングに設置したい
Q26. PlexやEmbyで映画や音楽をストリーミングできる?
A. GMKtec G9はPlexやEmbyのメディアサーバーとして利用可能
4K動画や高音質の音楽を家庭内&リモートでストリーミングできます。
📌 Plex & Embyの比較(どっちを選ぶ?)
| 機能 | Plex | Emby |
|---|---|---|
| 4K HDR再生 | ◯(条件付き) | ◎(ハードウェア支援あり) |
| リモート視聴 | ◎(無料で利用可) | ◯(有料機能あり) |
| ライブTV & DVR録画 | ◯(Plex Pass必須) | ◎(無料でも一部可) |
| 字幕管理 | ◎ | ◎ |
| トランスコーディング(動画変換) | ◯(ハードウェア対応) | ◎(軽量&高速) |
| カスタマイズ性 | △(制限あり) | ◎(オープンソースで自由度高い) |
💡 「Plexは手軽、Embyはカスタマイズ向け」
📌 Plex / Emby サーバーのセットアップ方法(簡単)
1️⃣ メディアサーバーをインストール
➡ Plex公式サイト または Emby公式サイト からダウンロード
2️⃣ メディアライブラリを設定
✔ 動画・音楽・写真のフォルダを指定
✔ ライブラリをスキャンしてメタデータを取得
3️⃣ ハードウェアアクセラレーションを有効化
✔ Plexの場合:設定→トランスコーディング→「ハードウェアアクセラレーションを有効化」
✔ Embyの場合:設定→「ハードウェアデコーディングを有効化」
4️⃣ ストリーミングの最適化
✔ LAN内では直接再生(Direct Play)を推奨
✔ リモート視聴時は「自動品質調整」をON
📌 Plex / Embyを快適にするポイント
✅ ネットワーク環境を最適化
✔ 2.5GbE対応のルーター & 有線LAN推奨(Wi-Fiは5GHz以上)
✔ リモート視聴時はアップロード帯域を確保(最低10Mbps以上推奨)
✅ NASや外付けHDDと連携
✔ 大容量の映画・音楽データを保存しやすい
✔ 外付けSSDならロード時間短縮&スムーズな再生が可能
✅ スマホやTVアプリと連携
✔ Plex / Embyアプリをスマホ・Fire TV・Apple TVにインストール
✔ ChromecastやAirPlayで大画面視聴
✅ メリット
✔ 映画・音楽を好きなデバイスでストリーミング
✔ 4K HDR対応で高画質再生可能
✔ NASや外付けHDDと組み合わせて大容量ライブラリを管理
❌ 注意点
⚠ 4KトランスコードはCPU負荷が高い(Direct Play推奨)
⚠ リモート視聴には十分なネット回線が必要(アップロード帯域に注意)
⚠ 無料版では一部機能が制限される(Plex Pass / Emby Premiereで解放)
💡 まとめ:Plex / Embyを使うのに向いている?
✅ 家庭内で映画・音楽を共有したい
✅ リモート視聴で外出先でもメディアを楽しみたい
✅ HTPCやNASと組み合わせて、完全なメディアセンターを構築したい
GMKtec 公式サイトの分解動画
SSD増設・初期化・設定方法
Q27. すでに持っているSSDを流用できる?(容量の違うSSDを混ぜてもいい?)
A. GMKtec G9は既存のSSDを流用可能
ただし、容量や接続規格(M.2 / SATA)を確認し、混在時の制約を理解しておくことが重要です。
📌 SSDの流用条件(使えるSSDは?)
| SSDタイプ | 互換性 | 注意点 |
|---|---|---|
| M.2 NVMe(PCIe 3.0/4.0) | ◎ 対応 | PCIe 4.0対応だが、速度はPCIe 3.0に制限 |
| M.2 SATA(SATA 3) | ◯ 対応 | NVMeスロットと共存不可のモデルあり |
| 2.5インチ SATA SSD | ◎ 対応 | 内部ストレージとして増設可能 |
| 外付けSSD(USB接続) | ◎ 対応 | USB 3.2 Gen 2推奨(最大10Gbps) |
💡 「M.2 NVMe & SATA SSDは流用OK。USB SSDも活用できる。」
📌 容量の違うSSDを混ぜるのはOK?
✅ 異なる容量のSSDを混ぜることは可能
✔ 個別ストレージとして使用するなら問題なし
✔ OS用とデータ用で分けて運用できる
❌ RAID構成にする場合は制限あり
⚠ RAID 0 / 1 は同じ容量・同じ規格のSSDが推奨
⚠ 異なる容量のSSDでRAIDを組むと、最小容量のSSDに合わせられる(無駄が出る)
| RAID構成 | 容量の違うSSDの影響 |
|---|---|
| RAID 0(ストライピング) | 最小容量のSSDに統一される(500GB + 1TB → 500GBとして認識) |
| RAID 1(ミラーリング) | 最小容量に統一され、余った容量は未使用(500GB + 1TB → 500GBのみ使用) |
| RAID 5/10(パリティ/ミラー+ストライプ) | 全SSDの最小容量に制限される |
💡 「単体運用なら容量違いOK。RAID用途なら同じSSD推奨」
📌 SSD流用時の設定ポイント
✅ OSのクローン・移行(別のSSDに交換する場合)
✔ 「Macrium Reflect」や「EaseUS Todo Backup」でクローン作成
✔ 新しいSSDに換装し、BIOSでブートドライブを変更
✅ フォーマット & パーティション調整
✔ 「ディスクの管理(Windows)」or gparted(Ubuntu) でフォーマット
✔ NTFS / exFAT(Windows)・ext4(Linux)を推奨
✅ SSDの寿命をチェック
✔ 「CrystalDiskInfo」で寿命(TBW / 使用時間)を確認
✔ 古いSSDはNASのキャッシュ用途などに活用可能
✅ メリット
✔ 既存のSSDを活用できるのでコスト削減
✔ M.2 + SATAでデュアルストレージ構成が可能
✔ OS用とデータ用でSSDを分けて最適な運用ができる
❌ 注意点
⚠ RAID構成時は同じ容量&規格のSSDが推奨
⚠ PCIe 4.0 SSDは互換性ありだが、速度はPCIe 3.0に制限される
⚠ 古いSSDの寿命をチェックして、バックアップを忘れずに
💡 まとめ:SSDを流用するなら?
✅ 単独で使うなら容量違いのSSDもOK
✅ RAIDを組むなら同じ容量・規格のSSDを推奨
✅ M.2 NVMe & SATA SSDを組み合わせて最適なストレージ環境を構築
Q28. GMKtec G9にM.2 SSDを増設できる?
A. GMKtec G9はM.2 NVMe SSDを増設できます。
PCIe 3.0 x4対応のM.2スロットがあり、高速ストレージを追加できます。
📌 M.2 SSDの増設スペック(どんなSSDが使える?)
| 項目 | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 対応規格 | M.2 NVMe(PCIe 3.0 x4) | PCIe 4.0 SSDも使用可(速度はPCIe 3.0に制限) |
| フォームファクター | M.2 2280 | 通常のM.2サイズ(長さ80mm)に対応 |
| 最大容量 | 2TB以上 | 公式には2TB推奨、4TB動作実績あり |
| M.2 SATA SSD | 非対応 | NVMe専用スロットのため、SATAタイプは不可 |
💡 「M.2 NVMe 2280ならOK。SATAタイプは非対応です。」
📌 M.2 SSDの増設手順(簡単)
1.GMKtec G9のカバーを開ける
✔ 底面のネジを外し、慎重にカバーを取り外す
2.M.2 NVMe SSDを装着
✔ スロットにSSDを斜めに差し込み、ネジで固定
3.SSDをフォーマット & 初期化
✔ Windowsなら「ディスクの管理」から新規ボリューム作成
✔ Ubuntuならsudo mkfs.ext4 /dev/nvme0n1 でフォーマット
📌 増設時のポイント(最適なSSD選び)
✅ 高速なNVMe SSDを選ぶ
✔ PCIe 3.0 x4対応のモデルが最適(例:WD Black SN750 / Samsung 970 EVO)
✔ PCIe 4.0 SSDも使用可(ただし、速度はPCIe 3.0相当)
✅ 放熱対策を考慮
✔ M.2 SSDは発熱しやすいため、ヒートシンク付きモデル推奨
✔ 長時間使用する場合は、冷却パッドや放熱シートを追加
✅ SSDの健康状態を定期チェック
✔ 「CrystalDiskInfo」や「SSD Toolbox」で寿命(TBW / 書き込み回数)を確認
✅ メリット
✔ 高速なNVMe SSDで読み書き速度UP
✔ 追加ストレージとして柔軟にカスタマイズ可能
✔ 最大2TB(実績4TB)まで増設でき、大容量ストレージ構築
❌ 注意点
⚠ M.2 SATA SSDは非対応(NVMe専用スロット)
⚠ PCIe 4.0 SSDを使っても速度はPCIe 3.0に制限
⚠ 発熱対策をしないと高負荷時に温度が上がりやすい
💡 まとめ:M.2 SSDを増設するなら?
✅ M.2 NVMe 2280(PCIe 3.0 x4)対応のSSDを選ぶ
✅ 2TB以上の大容量SSDも利用可能(4TB実績あり)
✅ ヒートシンク付きモデルを選ぶと発熱対策にも◎
Q29. M.2 SSDを追加したら、OSから認識されないときの対処法は?
A. M.2 SSDがOSから認識されない場合は、BIOS設定やフォーマットの確認が必要
接続不良や互換性の問題も考えられるため、順番にチェックしましょう。
📌 M.2 SSDが認識されないときのチェックポイント
| 問題の原因 | 対処方法 |
|---|---|
| 物理的な接続不良 | SSDを一度抜き差しし、正しく固定する |
| BIOSで認識されていない | BIOS設定を開き、M.2 SSDが検出されているか確認 |
| 未フォーマットのSSD | Windowsの「ディスクの管理」or Linuxのfdisk -lで確認し、フォーマット |
| NVMeとSATAの混同 | GMKtec G9はNVMe専用スロットのため、SATA M.2 SSDは非対応 |
| ドライバーが未インストール | 最新のIntel Rapid Storage Technology(IRST)ドライバーをインストール |
| MBR / GPTの不一致 | OSのインストール方式に合わせて、diskpart や gdisk で変換 |
💡 「物理接続 → BIOS確認 → フォーマット → ドライバー」の順でチェックしよう
📌 WindowsでSSDを認識させる方法
1️⃣ ディスクの管理を開く
- 「Windowsキー + X」→「ディスクの管理」を選択
- 新しいSSDが「未割り当て」と表示されているか確認
2️⃣ SSDをフォーマット(未割り当ての場合)
- SSDを右クリック → 「新しいシンプルボリューム」を選択
- NTFS / exFAT でフォーマット(OS用ならNTFS推奨)
3️⃣ デバイスマネージャーで確認
- 「Windowsキー + X」→「デバイスマネージャー」
- 「ディスクドライブ」にSSDが表示されているか確認
- 表示されていない場合:「ハードウェア変更のスキャン」を実行
📌 Linux(Ubuntu)でSSDを認識させる方法
1.SSDが認識されているか確認
lsblk
➡ /dev/nvme0n1 などが表示されているかチェック
2.フォーマットする(未フォーマットの場合)
sudo mkfs.ext4 /dev/nvme0n1
3.マウントして使用可能にする
sudo mount /dev/nvme0n1 /mnt
4.fstabに追加して自動マウント(オプション)
echo "/dev/nvme0n1 /mnt ext4 defaults 0 2" | sudo tee -a /etc/fstab
✅ メリット
✔ 物理接続や設定を確認することでSSDを正常に認識
✔ フォーマットすることでストレージとして使用可能
✔ OSの種類を問わず適切な設定で運用できる
❌ 注意点
⚠ M.2 SATA SSDは使用不可(NVMe専用スロット)
⚠ BIOSでSSDが認識されない場合は、互換性を確認
⚠ フォーマットするとデータが消えるので注意(事前にバックアップ推奨)
💡 まとめ:SSDが認識されないときの対処法は?
✅ 物理的に正しく装着されているか確認
✅ BIOSでSSDが検出されているかチェック
✅ Windows / Linuxのディスク管理ツールでフォーマット
Q30. SSDをRAID 1(ミラーリング)構成にする方法は?
A. GMKtec G9はソフトウェアRAID 1を構築可能
Windowsなら「ストレージプール」、Linuxなら「mdadm」を使用してデータの冗長性を確保できます。
📌 RAID 1(ミラーリング)の特徴
✅ メリット
✔ SSDの内容をリアルタイムで自動コピー(冗長性◎)
✔ 片方のSSDが故障してもデータを保持
✔ 読み込み速度は向上(書き込み速度は単体SSDと同等)
❌ 注意点
⚠ 2台のSSDが必要(同じ容量&規格推奨)
⚠ 片方のSSDに障害が出たら速やかに交換が必要
⚠ RAID 1はバックアップではない(別途バックアップ推奨)
💡 「データを守るためのRAID 1。 ただし完全なバックアップではないので要注意」
📌 WindowsでRAID 1を設定(ストレージプール使用)
1️⃣ RAID用のSSDを2台接続
2️⃣ 「ディスクの管理」でSSDを「未割り当て」にする
3️⃣ 「ストレージプール」を作成
- 「設定」→「ストレージ」→「ストレージスペースの管理」
- 「新しいプールとストレージスペースを作成」→「RAID 1(ミラー)」を選択
- SSD 2台を選択し、「作成」をクリック
4️⃣ フォーマットして完了
✔ NTFS形式でフォーマットし、RAID 1のディスクとして利用
📌 Ubuntu(Linux)でRAID 1を設定(mdadm使用)
1.mdadmをインストール
sudo apt update && sudo apt install mdadm -y
2.RAID 1を作成(/dev/nvme0n1 と /dev/nvme1n1を使用する例)
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/nvme0n1 /dev/nvme1n1
3.RAID 1の構成を確認
cat /proc/mdstat
4.ファイルシステムを作成&マウント
sudo mkfs.ext4 /dev/md0
sudo mount /dev/md0 /mnt
5.RAID設定を保存し、自動マウント
sudo mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
sudo update-initramfs -u
💡 「Ubuntu なら mdadm を使って RAID 1 を構築」
📌 RAID 1 の運用ポイント
✅ SSDの健康状態を定期チェック
✔ Windows:「CrystalDiskInfo」でSSDのS.M.A.R.T.情報を確認
✔ Linux:sudo smartctl -a /dev/nvme0n1 でS.M.A.R.T.情報を確認
✅ RAID 1の状態をチェック
✔ Windows:「ストレージプールの状態」でエラー確認
✔ Linux:cat /proc/mdstat で正常動作を確認
✅ SSDの交換方法(片方が故障した場合)
✔ Windows:「ストレージプール」で故障ディスクを交換
✔ Linux:新しいSSDを追加し、再同期
sudo mdadm --add /dev/md0 /dev/nvmeXn1
💡 まとめ:SSDをRAID 1にするなら?
✅ データを守るためにRAID 1を導入
✅ Windowsならストレージプール、Linuxならmdadmで構築
✅ 定期的にRAIDの状態&SSDの健康状態をチェック
Q31. Windows を完全に削除して Ubuntu だけで運用するには?
A. Windows を削除し、Ubuntu のみの環境にするには、Ubuntuをクリーンインストールします
インストール時に「ディスクを削除してUbuntuをインストール」を選択すればOK。
📌 Windows を削除してUbuntu をインストールする手順(簡単)
1.Ubuntuのインストールメディアを作成
✔ Ubuntu公式サイト からISOをダウンロード
✔ 「Rufus」や「balenaEtcher」でUSBメモリ(8GB以上)に書き込み
2.USBメモリからブート
✔ GMKtec G9を再起動し、「F7キー」を連打
✔ 「USBデバイス」を選択して起動
3.Ubuntuのインストール
✔ 言語・キーボードを選択し、「Ubuntuをインストール」へ
✔ 「ディスクを削除してUbuntuをインストール」を選択(Windows削除)
✔ 「インストール」をクリックし、設定完了後に再起動
4.必要なドライバー&ソフトをインストール
✔ 最新のアップデートを適用
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
✔ 必要なパッケージ(GPUドライバー・日本語入力)を追加
sudo apt install ubuntu-restricted-extras fcitx-mozc -y
📌 デュアルブートを解除する方法(Windowsのブートエントリを削除)
✅ Ubuntuをインストール後、Windowsの残骸を削除
1.GRUBメニューにWindowsが表示される場合は以下を実行
sudo update-grub
2.WindowsのEFIエントリを削除
sudo efibootmgr -b (WindowsのBoot番号) -B
3.確認
sudo efibootmgr
✅ ストレージのWindowsパーティションを削除
✔ Ubuntuの「ディスク」アプリ or gparted を使ってWindowsのパーティションを削除し、空き領域を拡張
💡 「Windowsのエントリを完全削除して、Ubuntu専用PCに」
📌 Ubuntu単独運用のメリット & デメリット
✅ メリット
✔ ディスク容量をフル活用(Windowsの領域を削除)
✔ 軽量&高速なLinux環境で快適運用
✔ 開発・サーバー用途に最適(Docker・VMなども動作◎)
❌ 注意点
⚠ Windows専用ソフト(Office・Adobe系)は使えなくなる
⚠ BIOS更新など、一部のツールがWindows専用(要USBブートで対応)
⚠ ゲーム用途には向かない(Steam Proton等で一部は動作)
💡 まとめ:Ubuntu単独運用に向いている?
✅ WindowsなしでLinux環境をフル活用したい
✅ 開発・サーバー用途で使いたい
✅ Windowsに依存しないワークフローを構築済み
Q32. OSをクリーンインストールするには?(USBメモリから再インストール)
A. OSをクリーンインストールするには、USBメモリから起動し、WindowsまたはUbuntuを再インストール。
手順に沿って進めれば簡単にリカバリーできます。
📌 OSクリーンインストールの準備(まずはこれを確認)
- USBメモリ(8GB以上)を用意
- インストールするOSのISOファイルをダウンロード
✔ Windows 11公式ダウンロード
✔ Ubuntu公式ダウンロード - 重要データをバックアップ(SSDのデータは消去される)
💡 「データを保存したい場合は、別のSSDや外付けHDDにバックアップを取る」
📌 Windows 11をクリーンインストールする方法
1.USBメディアを作成
✔ 「Rufus」または「Microsoftのメディア作成ツール」を使用して、Windows 11のUSBブートメディアを作成
2.USBメモリからブート
✔ GMKtec G9を再起動し、「F7キー」を連打
✔ 「USBデバイス」を選択して起動
3.Windowsをインストール
✔ 言語・キーボードを選択し、「今すぐインストール」をクリック
✔ 「カスタムインストール」を選び、既存のパーティションを削除
✔ SSDを選択し、Windowsを新規インストール
4.初期設定&ドライバー導入
✔ Windowsのセットアップを完了後、「Windows Update」を実行
✔ 必要なドライバーを適用(公式サイトまたは「Intel Driver & Support Assistant」を活用)
📌 Ubuntuをクリーンインストールする方法
1.Ubuntuのインストールメディアを作成
✔ 「Rufus」または「balenaEtcher」でUSBメモリにISOを書き込む
2.USBメモリからブート
✔ 「F7キー」を連打し、「USBデバイス」から起動
3.Ubuntuをインストール
✔ 言語・キーボードを選択し、「Ubuntuをインストール」へ
✔ 「ディスクを削除してUbuntuをインストール」を選択(クリーンインストール)
✔ 「インストール」をクリックし、設定完了後に再起動
4.必要なパッケージをインストール
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
✔ 最新ドライバーやアプリを追加(例:日本語入力)
sudo apt install fcitx-mozc -y
📌 クリーンインストール時の注意点
❌ SSDのデータがすべて消える(バックアップ必須)
❌ Windowsのライセンス認証を確認(デジタルライセンスは自動認証)
❌ BIOS設定を変更する場合は「UEFIモード」を推奨
✅ BIOSのリセット方法(必要な場合)
✔ 「F7キー」→ BIOSメニューで「Restore Defaults」を選択
✅ SSDをフォーマットしてクリーンな状態に
✔ Ubuntuなら sudo mkfs.ext4 /dev/nvme0n1
✔ Windowsなら「ディスクの管理」からフォーマット
💡 「UEFIモードでクリーンインストールすると安定」
💡 まとめ:OSをクリーンインストールするなら?
✅ Windows / UbuntuのUSBインストールメディアを作成
✅ 「F7キー」でUSBブートしてクリーンインストール
✅ インストール後に最新のアップデート&ドライバーを適用
Q33. BIOSでSSDのブート順を変更する方法は?
A. BIOS設定画面で「Boot Priority(ブート優先順位)」を変更すれば、起動するSSDを選択可能。
WindowsやUbuntuを複数のSSDにインストールした場合、ここで起動ドライブを指定できます。
📌 BIOSでブート順を変更する手順(簡単)
1.BIOSに入る
✔ GMKtec G9を再起動し、「F7キー」 を連打
✔ BIOS画面が開いたら、「Boot」タブを選択
2.起動ドライブを変更
✔ 「Boot Priority(ブート優先順位)」を開く
✔ 優先するSSD(Windows / Ubuntuが入ったドライブ)を一番上に設定
3.設定を保存して再起動
✔ 「F10キー」を押して「Save & Exit(保存して終了)」を選択
✔ PCが再起動し、指定したSSDからOSが起動
💡 「ブート順を変更すれば、複数のOSをインストールして切り替え可能」
📌 一時的に起動ドライブを変更する方法(F7キーで選択)
✅ SSDを切り替えたいが、毎回BIOSを開くのが面倒な場合
✔ PC起動時に 「F7キー」 を押し続ける
✔ 「Boot Manager(ブートマネージャー)」が表示される
✔ その場で起動するSSDを選択(次回起動時には元に戻る)
💡 「OSの切り替えを頻繁にするなら、F7キーでブートメニューを使うと便利」
📌 BIOSでSSDが表示されない場合の対処法
| 問題 | 対処法 |
|---|---|
| 新しいSSDがBIOSで認識されない | SSDが正しく接続されているか確認、BIOSの「Storage Configuration」をチェック |
| UEFIモードとレガシーモードの不一致 | BIOSの「Boot Mode」を「UEFI」に設定(Windows 11はUEFI必須) |
| OSのブートローダーが破損している | Windowsなら「修復ディスク」、Ubuntuならgrub-updateを試す |
✅ メリット
✔ 複数のOSを簡単に切り替え可能
✔ クリーンインストール後の起動ドライブ変更に便利
✔ USBメディアや外付けSSDからの起動も可能
❌ 注意点
⚠ ブート順を変更すると、間違ったSSDを起動する可能性あり(慎重に設定)
⚠ BIOSの設定を間違えると、OSが起動しなくなることも(元の設定をメモしておくと安心)
⚠ レガシーモード(CSM)とUEFIの設定ミスに注意(OSごとに最適な設定を確認)
💡 まとめ:BIOSでSSDのブート順を変更するなら?
✅ 「F7キー」でBIOSに入り、Boot Priorityを変更
✅ 一時的に変更するなら「F7キー」でブートメニューを活用
✅ SSDが表示されない場合は、BIOS設定や接続をチェック
コスパ・比較
Q34. GMKtec G9はNAS専用機(Synology/QNAP)と比べてどう?
A. GMKtec G9は柔軟性の高い自作NASとして活用可能。
Synology/QNAPのような専用NASより設定が自由で、性能も高いが、専用機の便利さには劣る部分も。
📌 GMKtec G9とNAS専用機(Synology/QNAP)の比較
| 項目 | GMKtec G9(自作NAS) | Synology/QNAP(専用NAS) |
|---|---|---|
| OSの自由度 | ◎ Ubuntu, TrueNAS, OpenMediaVaultなど選べる | △ DSM/QTSで制限あり |
| 性能(CPU/RAM) | ◎ 高性能(Intel CPU & 8GB以上のRAM) | ◯ 省電力CPUが主流 |
| RAID機能 | ◎ ソフトウェアRAID対応(mdadm, ZFS) | ◎ ハードウェアRAID / SHR対応 |
| ストレージ拡張性 | ◯ USB / M.2 / 外付けHDDで拡張 | ◎ ドライブベイ数が多いモデルあり |
| ネットワーク速度 | ◎ デュアル2.5GbEで高速通信 | ◎ 2.5GbE~10GbE対応モデルあり |
| 消費電力 | △ 約10~30W(設定次第) | ◎ 5~20Wで省電力 |
| セットアップの簡単さ | △ 自分で設定が必要 | ◎ 初心者でも簡単セットアップ |
| アプリ・機能 | ◎ Docker, Samba, Plex, Nextcloud など自由に導入可 | ◎ 専用アプリが豊富(Synology DSM/QNAP QTS) |
| コスト | ◎ コスパ良し(既存パーツを活用可) | △ 本体+HDDで高コスト |
💡 「GMKtec G9は自由度と性能重視、Synology/QNAPは簡単運用重視」
📌 GMKtec G9をNASとして使うメリット&デメリット
✅ メリット
✔ 高性能なCPU & メモリで、専用NASより高速
✔ OSを自由に選べる(Ubuntu, TrueNAS, OpenMediaVault)
✔ 2.5GbE対応で高速ファイル転送が可能
✔ Dockerや仮想環境も運用できる(柔軟なカスタマイズ)
✔ 既存のSSD/HDDを流用できるのでコスパ◎
❌ デメリット
⚠ 専用NASのような簡単セットアップはない(知識が必要)
⚠ RAID管理はソフトウェアRAIDが基本(ハードウェアRAIDなし)
⚠ 省電力性能は専用NASに劣る(長時間稼働のコストが少し高め)
💡 「初心者ならSynology/QNAP、カスタマイズしたいならGMKtec G9」
📌 GMKtec G9をNASとして活用するためのセットアップ例
✅ OS選び
✔ TrueNAS → ZFS対応、高信頼NAS向け
✔ OpenMediaVault → Debianベース、初心者向け
✔ Ubuntu Server + Samba → シンプルなファイルサーバー構築
✅ RAID構成(データ保護を重視する場合)
✔ RAID 1(ミラーリング):データを2台のSSD/HDDに同期して保存
✔ RAID 5(パリティ保護):3台以上のHDD/SSDで容量を確保しつつ冗長化
✅ ファイル共有 & ストリーミング機能
✔ Samba/NFS → Windows・Mac間でのファイル共有
✔ Plex/Emby → 動画や音楽をストリーミング
✔ Nextcloud → クラウドストレージとして活用
💡 まとめ:GMKtec G9をNAS専用機と比べると?
✅ カスタマイズ&高性能ならGMKtec G9
✅ 簡単セットアップ&省電力ならSynology/QNAP
✅ 低コストで自作NASを構築したいならGMKtec G9がオススメ
Q35. 長期運用した場合の電気代は?1ヶ月いくらくらい?
A. GMKtec G9の消費電力は約10~30W。
24時間稼働した場合、1ヶ月の電気代は約200~700円程度と省エネ。
📌 GMKtec G9の消費電力(どれくらい電気を使う?)
| 動作状態 | 消費電力(目安) | 1ヶ月の電気代(24時間稼働・1kWh=30円計算) |
|---|---|---|
| スリープ時 | 約2~3W | 約50円 |
| アイドル時(待機) | 約8~12W | 約200~300円 |
| 軽作業(ブラウジング・動画再生) | 約15~20W | 約400~500円 |
| 高負荷(ゲーム・動画編集・サーバー運用) | 約25~30W | 約600~700円 |
💡 「NASやホームサーバー用途なら月200~500円程度」
📌 電気代を抑えるための省電力設定
✅ BIOSで省電力モードを有効化
✔ 「CPU Power Management」を有効にする
✔ 「C-States(省電力ステート)」をONに
✅ Windowsで省電力設定を調整
✔ 「電源オプション」で「バランス」または「省電力モード」を選択
✔ 「ディスプレイの電源を切る時間」を短縮(例:5分)
✔ 「ハードディスクの電源を切る」設定を有効化
✅ Linux(Ubuntu)で省電力設定
✔ CPUの省電力モードを有効化
sudo apt install tlp -y
sudo systemctl enable tlp
✔ ディスクの省電力設定を適用
sudo hdparm -S 60 /dev/nvme0n1
✅ 不要なプロセスを停止して消費電力を抑える
✔ 使わないソフトを終了(バックグラウンドアプリを削減)
✔ ブラウザのタブを開きすぎない(メモリ使用量が増えると消費電力UP)
✅ メリット
✔ 24時間稼働でも電気代が安い(月500円以下が可能)
✔ 省電力設定をすればさらに電気代を節約
✔ ノートPC並みの消費電力でサーバー運用できる
❌ 注意点
⚠ 高負荷運用(ゲーム・動画エンコード)は電力消費が増える
⚠ UPS(無停電電源装置)を使うと追加の電力コストが発生
⚠ SSDや周辺機器の接続台数が多いと、消費電力も増える
💡 まとめ:長期運用の電気代はどのくらい?
✅ NAS・サーバー用途なら月200~500円程度
✅ 省電力設定をすればさらに節約可能
✅ 一般的なデスクトップPCよりも圧倒的に省エネ
Q36. 中古PCをNASにするのと比べて、どっちがコスパがいい?
A. GMKtec G9は低消費電力で長期運用向き。
一方、中古PCは初期コストが安いが、電気代やメンテナンスコストがかかる。用途次第で選ぼう。
📌 GMKtec G9 vs 中古PC(どちらがコスパ良い?)
| 比較項目 | GMKtec G9(ミニPC) | 中古PC(デスクトップ) |
|---|---|---|
| 初期コスト | △ 新品購入が必要(3~5万円) | ◎ 安い(1~3万円で入手可) |
| 消費電力 | ◎ 約10~30W(電気代:月200~700円) | △ 50~100W(電気代:月1,500円以上) |
| サイズ・静音性 | ◎ コンパクト&静音 | △ 大型&ファン音がうるさいことも |
| 対応OS | ◎ Ubuntu / TrueNAS / OpenMediaVaultなど自由 | ◎ 同じく自由 |
| ストレージ拡張性 | △ M.2 + USB外付けで対応 | ◎ HDDベイが多く、内部増設が容易 |
| ネットワーク性能 | ◎ デュアル2.5GbE対応 | △ 1GbEが多い(増設で対応) |
| メンテナンス性 | ◎ 新品なので寿命が長い | △ パーツの経年劣化リスクあり |
💡 「長期運用ならGMKtec G9。短期コスト重視なら中古PC」
📌 GMKtec G9を選ぶべき人は?
✅ 低消費電力で24時間運用したい
✅ コンパクト&静音なNASを構築したい
✅ デュアル2.5GbEで高速通信を活かしたい
✅ 新品の安定したハードウェアを使いたい
📌 中古PCを選ぶべき人は?
✅ 初期コストを抑えて安くNASを作りたい
✅ 内蔵HDDを複数台搭載したい(ストレージ拡張が容易)
✅ 消費電力が高くても気にしない(電気代がかかる可能性あり)
✅ 中古PCのメンテナンスができる(HDD・電源の劣化リスクあり)
📌 年間コスト比較(3年間運用した場合の目安)
| 項目 | GMKtec G9 | 中古PC(デスクトップ) |
|---|---|---|
| 本体価格 | 約4万円 | 約2万円 |
| 年間電気代 | 約3,600円(10W~30W想定) | 約18,000円(50W~100W想定) |
| メンテナンス費用 | ほぼ不要(新品) | HDD・電源交換が必要な場合あり(約1万円) |
| 合計(3年間) | 約5万円 | 約7~8万円 |
💡 「長期運用ならGMKtec G9の方がランニングコストが安い」
✅ メリット(GMKtec G9 vs 中古PC)
| GMKtec G9のメリット | 中古PCのメリット |
|---|---|
| 低消費電力で電気代が安い | 初期コストが安く、手軽にNASを作れる |
| 新品なので長期間安定運用できる | 拡張性が高く、HDDを複数搭載しやすい |
| デュアル2.5GbEで高速通信 | PCIeスロットで拡張しやすい(NIC・RAIDカード) |
✅ デメリット(GMKtec G9 vs 中古PC)
| GMKtec G9のデメリット | 中古PCのデメリット |
|---|---|
| 初期コストが高め(新品購入) | 消費電力が高く、長期運用で電気代がかかる |
| ストレージ増設はUSB接続がメイン | 中古品なので寿命が短い可能性あり |
💡 まとめ:どっちがコスパがいい?
✅ 短期的なコスト重視 → 中古PC(ただし、消費電力が高くメンテナンスが必要)
✅ 長期的なランニングコスト重視 → GMKtec G9(新品&省電力で安定運用)
✅ HDDをたくさん積むなら中古PC、静音&コンパクトならGMKtec G9
Q37. 他のミニPC(Beelink・Minisforum)と比べて優れている点は?
A. GMKtec G9はデュアル2.5GbE搭載でネットワーク性能が高い。
他のミニPCと比較すると、NASやホームサーバー用途に適した構成になっています。
📌 GMKtec G9 vs Beelink / Minisforum(どこが優れている?)
| 比較項目 | GMKtec G9 | Beelink / Minisforum |
|---|---|---|
| ネットワーク性能 | デュアル2.5GbE(高速通信◎) | 1GbEが多い(モデルによっては2.5GbE) |
| 消費電力 | 低消費電力(約10~30W) | モデルによるが、やや高め(20~50W) |
| 冷却性能 | ファン制御で静音性を確保 | 高性能モデルはファン音が大きくなる場合あり |
| OSの自由度 | Windows / Ubuntu / TrueNAS / OpenMediaVaultなど対応 | ほぼ同様(ただし一部BIOS設定が制限) |
| ストレージ構成 | M.2 NVMe + 2.5インチSSD/HDD対応 | モデルによるが、拡張性はほぼ同等 |
| 価格 | コスパ良し(3~5万円) | 性能次第(5~8万円のモデルも) |
💡 「GMKtec G9は特にNAS・サーバー用途に適したネットワーク性能が魅力」
📌 GMKtec G9を選ぶべき人は?
✅ デュアル2.5GbEを活かしてNASやファイルサーバーを構築したい
✅ 低消費電力&静音性を重視したい
✅ UbuntuやTrueNASなどをインストールして運用したい
✅ コスパの良いミニPCを探している
📌 Beelink / Minisforumを選ぶべき人は?
✅ CPU性能を重視する(Ryzen搭載モデルなど)
✅ ゲームや動画編集などの用途も考えている
✅ デスクトップPCの代わりに使いたい
✅ ビジュアルデザインや筐体の質感にこだわる
📌 GMKtec G9が優れている点まとめ
✅ デュアル2.5GbEで高速ファイル転送・サーバー用途に最適
✅ 低消費電力(約10~30W)で24時間運用もOK
✅ Ubuntu / TrueNAS / OpenMediaVault で自由にカスタマイズ可能
✅ 価格がリーズナブルでコスパ◎
💡 「特にネットワーク&省電力を重視するならGMKtec G9が最適」
Q38. GMKtec G9はなぜ安い?Synologyと何が違う?
A. GMKtec G9は一般的なPCパーツを採用し、ソフトウェアも自由に選べるため低コスト。
Synologyのような専用NASは独自OSや専用チップ、長期サポートを提供しているため価格が高め。
📌 GMKtec G9とSynology NASの違い(何が違う?)
| 比較項目 | GMKtec G9(ミニPC) | Synology NAS(専用機) |
|---|---|---|
| 価格 | 約3~5万円(本体のみ) | 約5~10万円(HDD別売) |
| OS | Ubuntu, TrueNAS, OpenMediaVault など自由に選択可能 | Synology DSM(独自OS) |
| CPU性能 | Intel製の一般向けCPU(高性能) | 省電力な専用チップ(ARM/Intel Celeron) |
| メモリ | 8GB~16GB(拡張可) | 2GB~8GB(拡張制限あり) |
| ネットワーク | デュアル2.5GbE(高速) | 1GbEが主流、一部高級モデルは2.5GbE~10GbE |
| RAID機能 | ソフトウェアRAID(mdadm, ZFS, Btrfs対応) | Synology Hybrid RAID(SHR)など独自RAID |
| ストレージ拡張性 | M.2 SSD & 外付けUSBストレージ対応 | HDDベイ搭載(最大8台以上のモデルあり) |
| セットアップの簡単さ | △ 手動設定が必要(知識必須) | ◎ 初心者でも簡単セットアップ |
| 省電力性 | △ 10W~30W(設定次第) | ◎ 5W~20W(低消費電力) |
| 専用アプリ | △ Plex, Docker, Sambaなどを自分で導入 | ◎ DSMで簡単にアプリを導入 |
| サポート・保証 | △ 一般的なPC保証(1年程度) | ◎ Synologyは長期アップデート&保証あり |
💡 「GMKtec G9はハードウェア性能が高く、コスパ◎。Synologyは専用機ならではの使いやすさが魅力。」
📌 GMKtec G9が安い理由(なぜコスパがいい?)
1.一般向けPCパーツを使用
✔ ミニPCとして汎用的なパーツを採用 → 大量生産でコストダウン
✔ Synologyは専用基板・独自ファームウェア開発 → コスト増加
2.OSが無料&オープンソース
✔ Ubuntu / TrueNAS / OpenMediaVault など無料OSが利用可能
✔ Synology DSMは独自開発 → 開発費が価格に反映
3.ストレージが自由(HDD別売)
✔ 自分で好きなSSD/HDDを選べる → コスト調整可能
✔ SynologyはHDD推奨モデルがあるため高価格化
4.保守・サポートが最小限
✔ 一般PCの保証のみ → 低コスト
✔ Synologyは長期アップデート&企業向けサポート → 高価格化
💡 「GMKtec G9はハードの自由度が高く、OSやストレージを自分で選べるから安い」
📌 GMKtec G9を選ぶべき人は?
✅ コスパ重視でNASを構築したい(性能が高く低価格)
✅ Linuxやサーバー構築に慣れている(手動設定がOKな人)
✅ 2.5GbEで高速ファイル転送を活かしたい
✅ Dockerや仮想環境も運用したい(Synologyより柔軟)
📌 Synology NASを選ぶべき人は?
✅ 初心者でも簡単に使えるNASが欲しい(DSMで簡単セットアップ)
✅ 長期アップデート&サポートが必要(ビジネス用途向け)
✅ 専用アプリを手軽に使いたい(Synology Drive, Moments, Surveillance Stationなど)
✅ 省電力で安定した長時間運用をしたい(専用設計で最適化)
💡 まとめ:GMKtec G9 vs Synology NAS(どっちがいい?)
✅ 「コスパ最強・自由度の高いNAS → GMKtec G9」
✅ 「初心者でも簡単&安心のNAS → Synology」
✅ 「Linuxや自作サーバーに慣れているならGMKtec G9の方が安くて高性能」
GMKtec G9の「PC+NAS」活用法
Q39. 「最初は普通のPC、後からNASにする」ってどういうこと?
A. GMKtec G9は最初は通常のWindows PCとして使い、後からNAS専用機として転用できます。
Windowsのままファイル共有サーバーにすることも、UbuntuやTrueNASをインストールして完全なNASにすることも可能。
📌 「普通のPC → NAS」にする流れ(どんな使い方ができる?)
| フェーズ | 用途 | 設定方法 |
|---|---|---|
| ① 普通のPCとして使用 | ブラウジング / 動画視聴 / 仕事用PC | Windows 11でそのまま利用 |
| ② 簡易NASとして利用 | ファイル共有 / メディアサーバー | Windowsの「ファイル共有」やPlexを設定 |
| ③ 本格的なNAS化 | TrueNAS / OpenMediaVaultで24時間運用 | 別のSSDにNAS用OSをインストール |
💡 「最初はPCとして使い、不要になったらNAS専用機にできる」
📌 ステップ①:まずは普通のPCとして使う(特に設定不要)
✔ GMKtec G9にWindows 11がプリインストールされているので、そのまま使用可能
✔ 動画視聴・Webブラウジング・オフィス作業・ゲームなど通常のPC用途で利用
📌 ステップ②:Windowsのまま簡易NASとして使う(設定3分)
✅ ファイル共有機能を使う(家庭内LANで共有)
1️⃣ 共有フォルダを作成し、右クリック → 「プロパティ」 → 「共有」タブへ
2️⃣ 「詳細な共有」をクリックし、「このフォルダーを共有する」にチェック
3️⃣ ネットワーク上の他のPCから「\[GMKtecのIPアドレス]」でアクセス可能
✅ メディアサーバー(Plex / Emby)を導入(映画・音楽をストリーミング)
✔ Plex をインストールし、ライブラリを追加
✔ スマホ・タブレット・テレビからストリーミング視聴可能
📌 ステップ③:本格的なNASにする(Windowsを削除して専用OSに)
✅ Windowsを削除してNAS用OSをインストール
✔ TrueNAS / OpenMediaVault をUSBメモリからインストール
✔ RAID構成やクラウド同期を設定し、本格的なファイルサーバーへ
✅ 常時稼働するための省電力設定
✔ ファン制御を最適化し、冷却&静音化
✔ Wake-on-LAN(WOL)を有効にしてリモートで起動可能に
✅ メリット
✔ 最初は普通のPCとして使い、用途が変わっても無駄にならない
✔ Windowsのままファイル共有・メディアサーバーとして活用可能
✔ TrueNASなどを導入すれば専用NAS機と同等の機能を実現
❌ 注意点
⚠ WindowsのままNAS化すると機能が限定的(専用OSの方が安定)
⚠ HDDを増設しないと本格的なNAS運用には向かない(USB拡張で対応可)
⚠ 24時間稼働するなら冷却対策が必要(ファン制御 or 冷却パッド推奨)
💡 まとめ:「普通のPC → NAS化」が向いている人は?
✅ 最初はPC用途で使い、後からNASに転用したい
✅ Windowsのまま手軽にファイル共有やメディアサーバーを作りたい
✅ 本格的なNASを構築する前に、試験運用してみたい
Q40. 一時的にPCとしてもNASとしても使う(デュアル用途)は可能?
A. GMKtec G9は「PC」と「NAS」を同時に使うことが可能です。
WindowsやUbuntuを動かしながら、NASとしてファイル共有やメディアサーバー機能を提供できます。
📌 デュアル用途(PC & NAS)の運用方法(どうやって使う?)
| 運用方法 | OS | 用途 |
|---|---|---|
| ① WindowsのままNAS化 | Windows 11 | 普通のPC + ネットワーク共有 / メディアサーバー |
| ② Ubuntuでデュアル用途 | Ubuntu Desktop | 普通のPC + Samba / Nextcloud / Docker活用 |
| ③ 仮想環境を活用(VM) | Windows / Linux + 仮想環境 | 片方をPC用途、もう片方をNAS用途 |
| ④ デュアルブート | Windows & TrueNAS | 必要に応じてOSを切り替え(同時利用は不可) |
💡 「PCを使いながらNASとしても動作可能」
📌 方法①:Windowsを使いながら簡易NASとして利用(最も簡単)
✅ ファイル共有を有効化(家庭内LANでファイル共有)
- 共有フォルダを作成し、右クリック → 「プロパティ」 → 「共有」タブへ
- 「詳細な共有」をクリックし、「このフォルダーを共有する」にチェック
- ネットワーク上の他のPCから「\[GMKtecのIPアドレス]」でアクセス
✅ Plex / Emby でメディアサーバーとして活用
✔ Plex や Emby をインストールし、映画・音楽をストリーミング
✅ Wake-on-LAN(WOL)を設定し、リモートで起動するように
✔ ルーターのポート開放で外部アクセスも可能になる
💡 「Windowsを使いながら、家庭内のNASとしても動作」
📌 方法②:UbuntuでPC & NASを両立(Linuxユーザー向け)
✅ Sambaを設定してWindows / macOSとファイル共有
sudo apt update && sudo apt install samba -y
sudo nano /etc/samba/smb.conf
✔ 共有フォルダを設定し、LAN内でアクセス可能になる
✅ Dockerでクラウドサービス(Nextcloudなど)を運用
sudo apt install docker.io -y
sudo docker run -d -p 8080:80 nextcloud
✔ Webブラウザからアクセスし、自宅クラウドストレージとして利用できる
✅ デュアルモニターにして、PC作業しながらNAS運用も可能
💡 「LinuxならPC & NASをシームレスに運用」
📌 方法③:仮想環境を活用(Windows & TrueNASを同時利用)
✅ Windows上で仮想マシン(VM)を動作
✔ VirtualBox / VMware / Hyper-V で TrueNAS を仮想環境にインストール
✔ WindowsをメインPCとして使いながら、バックグラウンドでNAS運用
✅ Ubuntu + KVM で Windows と TrueNAS を両立
✔ Linux上で仮想マシンを動作させ、片方をNAS専用、もう片方をデスクトップ環境に
💡 「仮想環境を活用すれば、1台のPCでPC & NASを同時運用可能」
📌 方法④:デュアルブートでPC & NASを切り替え(同時利用は不可)
✅ Windows & TrueNAS をデュアルブートに設定
1️⃣ Windowsをインストール(既存のままでもOK)
2️⃣ 別のSSDにTrueNASをインストール
3️⃣ BIOSで起動するOSを選択(または「F7キー」でブートメニューから選択)
💡 「PC用途の時はWindows、NAS用途の時はTrueNASを起動」
✅ メリット
✔ 1台のPCで「PC + NAS」を両立できる
✔ 仮想環境を使えば、同時にPC & NASを運用可能
✔ Windowsのままでもファイル共有 & メディアサーバーが構築可能
❌ 注意点
⚠ WindowsのままNAS化すると機能が限定される(専用OSの方が安定)
⚠ 24時間運用なら冷却対策が必要(ファン制御 or 冷却パッド推奨)
⚠ 仮想環境は設定がやや難しい(リソース配分に注意)
💡 まとめ:「PC & NASのデュアル用途」はどう運用する?
- Windowsのまま簡単にNAS化 → ファイル共有 & Plex
- UbuntuでPC & NASを両立 → Samba + Docker
- 仮想環境を活用 → Windows & TrueNASの同時運用
- デュアルブートで用途ごとに切り替え → Windows & TrueNAS
Q41.Linuxサーバー+PCとして運用する方法は?
A. GMKtec G9はLinuxをインストールすれば「サーバー」と「デスクトップPC」の両方で運用可能です。
UbuntuやDebianなどを導入し、GUIを使いながらWebサーバーやファイル共有も同時に動作させることができます。
📌 Linuxサーバー+PCの運用方法(どの使い方ができる?)
| 運用方法 | 用途 | 設定方法 |
|---|---|---|
| ① Linuxデスクトップ + 軽量サーバー | 普通のPC + Web / ファイルサーバー | Ubuntu + Apache / Samba |
| ② GUIなしのサーバー + リモートPC運用 | サーバーとして24時間稼働し、別PCから接続 | Ubuntu Server + SSH / RDP |
| ③ 仮想環境(KVM / Docker)でサーバー管理 | 仮想環境で複数のサーバーを管理しつつPCとしても使用 | KVM / Dockerを導入 |
💡 「デスクトップ環境を維持しながら、サーバー機能を活用」
📌 方法①:Ubuntuデスクトップ+軽量サーバー(初心者向け)
✅ Ubuntu Desktop をインストール
✔ GUIがあるので、通常のPCとしても利用可能
✔ サーバー機能を追加して「PC + サーバー」の両立が可能
✅ ファイルサーバー(Samba/NFS)を導入
✔ Windowsと共有する場合(Samba)
sudo apt update && sudo apt install samba -y
sudo nano /etc/samba/smb.conf
✔ MacやLinuxと共有する場合(NFS)
sudo apt install nfs-kernel-server -y
sudo nano /etc/exports
💡 「デスクトップ環境を維持しつつ、ファイルサーバーを運用」
✅ Webサーバー(Apache / Nginx)を導入
✔ Apache(簡単セットアップ)
sudo apt install apache2 -y
✔ Nginx(軽量&高性能)
sudo apt install nginx -y
💡 「PCで作業しながら、Webサーバーを運用できる」
📌 方法②:GUIなしのLinuxサーバー + 別PCからリモート操作(中級者向け)
✅ Ubuntu Server をインストール
✔ GUIなしで省リソース化(メモリ・CPU負荷を抑える)
✔ 別のPCからSSHやRDPで接続し、遠隔管理
✅ SSHでリモート接続(Windows / macOS / Linux から操作可能)
✔ SSHサーバーをインストール
sudo apt install openssh-server -y
✔ 別のPCから接続(WindowsならPowerShell)
ssh ユーザー名@サーバーのIPアドレス
✅ リモートデスクトップ環境を追加(必要な場合)
✔ XRDPを導入してWindowsからリモートデスクトップ接続可能
sudo apt install xrdp -y
💡 「メインPCとしては使わず、サーバー専用機として運用」
📌 方法③:仮想環境(KVM / Docker)でサーバー管理(上級者向け)
✅ KVM(仮想マシン)を導入し、複数のサーバーを運用
✔ 仮想環境を作成
sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon-system virt-manager -y
✔ 仮想マシンを管理
virt-manager
💡 「Linux上でWindowsや別のLinuxサーバーを動作させることも可能」
✅ Dockerでアプリごとにサーバー機能を管理
✔ Dockerをインストール
sudo apt install docker.io -y
✔ Nextcloud(クラウドストレージ)を導入
sudo docker run -d -p 8080:80 nextcloud
💡 「Dockerを活用すれば、サーバーをコンテナ化して柔軟に運用可能」
✅ メリット
✔ 1台のPCで「デスクトップPC + サーバー」を両立
✔ 軽量Linuxならリソースを節約しながら24時間運用可能
✔ 仮想環境やDockerを活用すれば、複数のサーバーを統合運用できる
❌ 注意点
⚠ PC作業とサーバー運用を同時にすると負荷がかかる
⚠ GUIなしのUbuntu Serverはコマンド操作が必須(SSHやRDPを活用)
⚠ 長時間運用するなら冷却対策が必要(ファン制御 & 放熱対策)
💡 まとめ:「Linuxサーバー + PC」の運用に向いている人は?
✅ デスクトップPCを使いながら、ファイル共有やWebサーバーを動かしたい
✅ GUIなしのLinuxサーバーをリモート管理し、24時間稼働させたい
✅ 仮想環境やDockerを活用し、複数のサーバーを同時運用したい
Q42.GMKtec G9でDockerを動かしてアプリサーバーを構築できる?
A. GMKtec G9はDockerを動かせるので、アプリサーバー構築ができる
低消費電力&デュアル2.5GbEを活かして、クラウドストレージ・メディアサーバー・開発環境などを柔軟に構築できます。
📌 Dockerとは?(なぜ便利?)
✅ アプリをコンテナ化して簡単に導入・管理できる
✅ 仮想マシンより軽量&高速(低スペックでも快適動作)
✅ 複数のアプリを同時に動作可能(Webサーバー, DB, クラウドストレージ etc.)
✅ 環境を汚さずに、異なるOSやパッケージのアプリを動作できる
💡 「GMKtec G9なら、Dockerでサーバー用途を簡単に拡張できる」
📌 GMKtec G9にDockerをインストールする方法(簡単)
1.Ubuntuをインストール(Windowsでも可能だがLinux推奨)
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
2.Dockerをインストール
sudo apt install docker.io -y
✔ インストール後、Dockerのバージョン確認
docker --version
3.Dockerを自動起動&ユーザーを追加
sudo systemctl enable docker
sudo usermod -aG docker $USER
✔ PCを再起動し、docker ps で動作確認
💡 「これでDocker環境が準備完了」
📌 おすすめのDockerアプリ(すぐに使える)
1.Nextcloud(自宅クラウドストレージ)
docker run -d -p 8080:80 nextcloud
✔ Webブラウザで http://[GMKtec G9のIP]:8080 にアクセス
2.Plex(メディアサーバー)
docker run -d --network=host --name plex -e PLEX_CLAIM= -v /path/to/media:/media plexinc/pms-docker
✔ 動画や音楽をスマホやTVでストリーミング
3.WordPress(ブログ・Webサイト)
docker run -d --name mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root -e MYSQL_DATABASE=wordpress mysql:5.7
docker run -d --name wordpress --link mysql:mysql -p 8081:80 wordpress
✔ http://[GMKtec G9のIP]:8081 でWordPressのセットアップ画面へ
4.Home Assistant(スマートホーム管理)
docker run -d --name homeassistant --privileged --restart=unless-stopped -v /config:/config -p 8123:8123 homeassistant/home-assistant
✔ IoTデバイスを管理し、自宅をスマートホーム化
5.PostgreSQL(データベースサーバー)
docker run -d --name postgres -e POSTGRES_PASSWORD=mysecretpassword -p 5432:5432 postgres
✔ Webアプリや開発用のDBサーバーとして活用
💡 「Dockerを活用すれば、GMKtec G9が強力なアプリサーバーに」
📌 Docker Composeを使って複数のコンテナを管理(便利)
1.Docker Composeをインストール
sudo apt install docker-compose -y
2.docker-compose.yml を作成(例:WordPress + MySQL)
version: '3'
services:
db:
image: mysql:5.7
restart: always
environment:
MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
MYSQL_DATABASE: wordpress
wordpress:
image: wordpress
restart: always
ports:
- "8081:80"
environment:
WORDPRESS_DB_HOST: db
WORDPRESS_DB_USER: root
WORDPRESS_DB_PASSWORD: root
3.Docker Composeで起動
docker-compose up -d
💡 「Composeを使えば、複雑なアプリも簡単に管理できる」
✅ メリット
✔ 簡単にサーバー機能を追加できる(アプリの導入がラク)
✔ 仮想マシンより軽量で高速(リソース節約)
✔ Webサーバー, メディアサーバー, クラウドストレージを1台で運用可能
❌ 注意点
⚠ ストレージの容量を確保(SSD 500GB以上推奨)
⚠ メモリ8GB以上推奨(複数コンテナを動かすなら16GBあると安心)
⚠ ネットワーク設定(ポート管理)を最適化しないと競合の可能性あり
💡 まとめ:GMKtec G9でDockerを活用するなら?
✅ クラウドストレージ(Nextcloud)やメディアサーバー(Plex)を構築
✅ 開発環境(WordPress, PostgreSQL, Node.jsなど)を簡単に導入
✅ 仮想マシンより軽量なサーバー運用を実現
Q43.WindowsとLinuxでファイルを共有する最適な方法は?
A. WindowsとLinux間でファイルを共有する方法はいくつかありますが、用途に応じて「Samba」「NFS」「SSH(SFTP)」などを選ぶのがベスト
📌 用途別の最適なファイル共有方法(どれを選ぶ?)
| 方法 | おすすめ用途 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| Samba(SMB) | WindowsとLinux間のファイル共有(家庭内LAN) | Windowsの「ネットワーク共有」と互換性◎ | セットアップが必要 |
| NFS(Network File System) | Linux間やLinux中心の環境 | 軽量&高速(Windowsも設定すれば使える) | Windowsの設定が面倒 |
| SSH(SFTP / SCP) | リモートサーバーとのファイル転送 | セキュアで外部からもアクセス可能 | 共有フォルダとしては不便 |
| クラウド同期(Nextcloud, Syncthing) | 自動同期したい場合 | デバイス間で常に最新のデータを維持できる | サーバー構築が必要 |
| USBストレージ | 物理的にデータを移動 | どんな環境でも使える | 手動でコピーが必要 |
💡 「LAN内ならSamba、Linux主体ならNFS、外部アクセスならSFTP」
📌 方法①:Samba(SMB)でWindowsとLinuxを共有(おすすめ)
1.Linux側にSambaをインストール(Ubuntuの場合)
sudo apt update && sudo apt install samba -y
2.共有フォルダを作成
mkdir -p /home/username/share
chmod 777 /home/username/share
3.Samba の設定を編集
sudo nano /etc/samba/smb.conf
✔ smb.conf の最後に以下を追加(共有設定)
[SharedFolder]
path = /home/username/share
browseable = yes
writable = yes
guest ok = yes
create mask = 0777
directory mask = 0777
4.Sambaを再起動
sudo systemctl restart smbd
5.Windows側でネットワークフォルダにアクセス
✔ エクスプローラーのアドレスバーに以下を入力
\\[LinuxのIPアドレス]\SharedFolder
✔ ネットワークドライブとしてマウントすれば、WindowsからLinuxのフォルダに簡単にアクセス可能
💡 「Windowsのネットワーク共有と同じ感覚で使えるので便利」
📌 方法②:NFS(Network File System)でLinux⇔Windows共有(高速)
1. Linux側にNFSサーバーをインストール(Ubuntu)
sudo apt update && sudo apt install nfs-kernel-server -y
2. 共有フォルダを作成
mkdir -p /mnt/shared_nfs
chmod 777 /mnt/shared_nfs
3. /etc/exports に共有設定を追加
sudo nano /etc/exports
✔ 以下の行を追加(Windowsからアクセスする場合)
/mnt/shared_nfs *(rw,sync,no_subtree_check)
4. NFSサーバーを再起動
sudo exportfs -a
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
5. Windows側でNFS機能を有効化(Windows 10/11 Pro限定)
✔ 「Windowsの機能の有効化と無効化」→ 「NFS クライアント」をONにする
✔ エクスプローラーで以下を入力
\\[LinuxのIPアドレス]\mnt\shared_nfs
💡 「NFSはLinux環境なら軽量&高速。WindowsでもPro版なら利用可能」
📌 方法③:SSH(SFTP / SCP)でファイル転送(リモート向け)
1. Linux側にSSHサーバーをインストール
sudo apt install openssh-server -y
2. Windows側でWinSCPやFileZillaをインストール
✔ ホストに「LinuxのIPアドレス」
✔ ユーザー名・パスワードを入力
✔ SFTPでセキュアにファイルを転送可能
💡 「リモートサーバーにアクセスするならSFTPが最適」
📌 方法④:Nextcloud / Syncthing でクラウド同期(自動化)
✅ NextcloudをDockerでセットアップ(Linux側)
docker run -d -p 8080:80 nextcloud
✔ Webブラウザで http://[LinuxのIP]:8080 にアクセスして設定
✅ Windows側にNextcloudクライアントをインストールし、同期フォルダを指定
💡 「NextcloudやSyncthingなら、デバイス間で常にデータを最新に保てる」
📌 結論:WindowsとLinuxのファイル共有、どの方法が最適?
✅ 家庭内LANで簡単に共有したい → Samba(SMB)
✅ Linux主体の環境で高速に共有したい → NFS(Linux推奨)
✅ リモートで安全に転送したい → SSH(SFTP / SCP)
✅ クラウド的に自動同期したい → Nextcloud / Syncthing
💡 「用途に応じて最適な方法を選べば、WindowsとLinuxのファイル共有は簡単」
メンテナンス・耐久性
Q44.長期間使うとファンのホコリ対策は必要?
A. はい、長期間運用するとファンにホコリが溜まり、冷却性能が低下するため、定期的なメンテナンスが必要です
ホコリが溜まると、PCの温度が上がり、動作が不安定になることもあるため、掃除や対策をしましょう。
📌 ファンのホコリが溜まるとどうなる?(放置すると危険)
| 問題 | 影響 | 対策 |
|---|---|---|
| 冷却性能の低下 | CPU温度が上昇し、動作が不安定に | 定期的にホコリを除去 |
| ファンの騒音増加 | ホコリが溜まるとファンが高速回転してうるさくなる | フィルター設置・掃除 |
| パーツの寿命短縮 | 熱による劣化が早まり、SSDや電源にも影響 | 適切なエアフローを確保 |
| 電力消費の増加 | 冷却のためにファンがフル稼働し、消費電力が増える | 低負荷時にファン回転を抑える設定 |
💡 「ホコリ対策をしないと、PCの温度上昇&寿命短縮のリスクあり」
📌 簡単にできるホコリ対策(放置せずにメンテナンス)
1. 定期的にファン&通気口のホコリを掃除
✔ エアダスター(缶スプレー)で吹き飛ばす(1~3ヶ月ごと推奨)
✔ 掃除機(ブラシ付き)で吸い取る(通気口を重点的に)
✔ 綿棒やブラシで細かい部分のホコリを取る
2. フィルターや防塵カバーを使う
✔ メッシュフィルターを通気口に設置(ホコリの侵入を防ぐ)
✔ **不織布シート(エアコンフィルター)**をカットして貼る
✔ 本体を床置きしない(ホコリが溜まりやすくなる)
3. ファンの回転数を調整し、ホコリの吸い込みを減らす
✔ BIOSでファンの回転数を調整(低負荷時は低回転にする)
✔ ファンコントロールソフト(SpeedFan, FanControl)を活用
4. 設置場所を工夫する
✔ 床やカーペットの上に直接置かない(ホコリが溜まりやすい)
✔ 壁や家具に密着させず、適度なエアフローを確保
💡 「ホコリの侵入を防ぎつつ、定期的な掃除をするのがベスト」
📌 ファン掃除の具体的な手順(簡単メンテナンス)
1. PCの電源を切り、ケーブルを抜く
2. エアダスターでファンのホコリを吹き飛ばす
✔ 吸気口・排気口・ファンの隙間を重点的に
✔ 回転中のファンにエアを吹きかけると故障の原因になるので注意
3. ブラシや綿棒で細かいホコリを除去
✔ 掃除機を使う場合は、ブラシ付きノズルで優しく吸い取る
4. 必要ならファンを分解して清掃(上級者向け)
✔ ドライバーでファンを取り外し、水洗い or アルコールで拭き取る
✔ 完全に乾燥させてから元に戻す
💡 「エアダスターで吹き飛ばすだけでも効果あり」
✅ メリット
✔ PCの温度上昇を防ぎ、安定動作を維持
✔ ファンの騒音を抑え、静音性UP
✔ 電力消費を抑えて、長時間稼働時の効率UP
❌ 注意点
⚠ ファンに直接手を触れない(故障の原因になる)
⚠ エアダスターを近づけすぎない(静電気や液体噴射のリスク)
⚠ 分解清掃は慎重に(保証が切れる可能性あり)
💡 まとめ:長期間運用時のホコリ対策は?
✅ 定期的な掃除(1~3ヶ月ごと)で冷却性能を維持
✅ フィルターや設置場所を工夫し、ホコリの侵入を減らす
✅ ファンの回転数を最適化し、ホコリの吸い込みを抑える
Q45.24時間稼働させた場合の耐久性は?寿命はどれくらい?
A. GMKtec G9は24時間稼働が可能な設計ですが、冷却や電源管理を適切に行うことで寿命を延ばせます。
CPUやメモリは長寿命ですが、ストレージ(SSD)や冷却ファンの耐久性がカギになります。
📌 各パーツの耐久性(寿命はどれくらい?)
| パーツ | 寿命の目安(24時間稼働時) | 主な劣化要因 | 延命対策 |
|---|---|---|---|
| CPU | 10年以上(ほぼ無劣化) | 高温状態が続くと寿命短縮 | 冷却を最適化(温度を70℃以下に保つ) |
| メモリ(RAM) | 10年以上(劣化少ない) | 不良セクタの発生 | 定期的にメモリチェック |
| SSD(NVMe / SATA) | 約5~10年(書き込み頻度による) | 書き込み寿命(TBW) | DRAMキャッシュ付きSSDを使用 |
| 冷却ファン | 約2~5年(消耗品) | ホコリ詰まり・軸の摩耗 | 定期的な清掃&静音ファンに交換 |
| 電源(ACアダプター) | 約3~5年(発熱による劣化) | 過熱・電圧変動 | UPS(無停電電源装置)で保護 |
💡 「CPU・メモリは長寿命。SSD・ファン・電源は消耗品なので交換前提です」
📌 24時間稼働時の耐久性を向上させる方法(長持ちさせるには?)
1.CPU・SSDの温度管理を徹底(寿命UP)
- CPU温度は 70℃以下、SSD温度は 50℃以下 を維持
- 高温時に性能を落とさないように、ファンコントロールを調整
2.SSDの書き込み負荷を減らす(SSD寿命UP)
- ログ・キャッシュの書き込みをRAMディスクに変更
- 「fstrim」コマンドで定期的にSSDの最適化
sudo systemctl enable fstrim.timer
💡 「SSDの書き込みを抑えると寿命が大幅に延びる」
3.冷却ファンをメンテナンス(長期間安定稼働)
- 3ヶ月に1回、エアダスターでホコリを除去
- ファンの異音が出始めたら交換(摩耗で寿命が短くなる)
4.電源管理を最適化(電源トラブル対策)
- UPS(無停電電源装置)を導入(停電や電圧変動から保護)
- 「高効率なACアダプター」を使用し、発熱を抑える
5.長期間使うなら予備のSSD&ファンを用意(交換前提)
- SSDは5年以上使うなら交換準備(特に書き込み頻度が高い場合)
- ファンは3~5年で交換(静音ファンにするとさらに快適)
📌 耐久性を考慮した運用のポイント(どのくらい使える?)
| 運用方法 | 想定寿命 | ポイント |
|---|---|---|
| 通常使用(PC用途) | 5年以上 | 毎日数時間の使用なら問題なし |
| ホームサーバー(軽負荷) | 3~5年(SSD交換前提) | 定期的な冷却&SSDチェックが必要 |
| 高負荷サーバー(Docker, Plex, AI推論) | 2~4年(メンテナンス必須) | CPU・SSDの温度管理&冷却対策が重要 |
💡 「ホームサーバー用途なら5年は使える。SSD&ファンは消耗品と考えよう」
✅ メリット
✔ CPU・メモリは長寿命で24時間稼働OK
✔ SSDやファンのメンテナンスをすれば長期間使える
✔ UPSや冷却対策をすれば、安定したサーバー運用ができる
❌ 注意点
⚠ SSD・ファン・電源は定期交換が必要(特にSSDのTBWをチェック)
⚠ 冷却が不十分だと寿命が短くなる(温度管理を徹底)
⚠ UPSがないと停電リスクがある(RAID崩壊の危険)
💡 まとめ:24時間運用時の耐久性は?
✅ CPU・メモリは10年以上使える(温度管理をしっかり)
✅ SSDは5年程度で交換前提(書き込み頻度を抑えると長持ち)
✅ 冷却ファン・電源アダプターは3~5年で交換(ホコリ対策必須)
Q46.定期的なメンテナンスは必要?NAS運用で気をつけることは?
A. GMKtec G9をNAS運用する場合、定期的なメンテナンスが必要
特に「ストレージ管理」「冷却対策」「データバックアップ」の3点を意識することで、長期間安定して運用できます。
📌 NAS運用で定期的にチェックすべきポイント(最低限これをやる)
| チェック項目 | 頻度 | 具体的な対策 |
|---|---|---|
| ストレージの健康状態(SSD/HDD) | 月1回 | S.M.A.R.T.情報を確認 (smartctl / CrystalDiskInfo) |
| データバックアップ | 週1回~月1回 | 別のHDD/NAS/クラウドに定期バックアップ |
| RAIDの状態チェック(RAID運用時) | 週1回 | mdadm --detail /dev/md0(Linux)でRAID状態を確認 |
| 冷却ファン&通気口のホコリ掃除 | 3ヶ月ごと | エアダスターで清掃し、ファンの動作音を確認 |
| 電源の異常チェック(UPS使用時) | 3ヶ月ごと | UPSのバッテリー残量&動作確認 |
| OS・ソフトウェアのアップデート | 月1回 | sudo apt update && sudo apt upgrade -y(Linux) |
| ログの確認(異常発生時のみ) | トラブル時 | /var/log/syslog や Windowsのイベントビューアを確認 |
💡 「NAS運用のポイントは、ストレージ・冷却・バックアップの3点」
📌 ストレージの健康チェック(SSD / HDDの寿命を確認)
✅ LinuxでSSD/HDDのS.M.A.R.T.チェック(月1回)
sudo apt install smartmontools -y
sudo smartctl -a /dev/nvme0n1 # NVMe SSDの場合
sudo smartctl -a /dev/sda # SATA HDD/SSDの場合
✔ 「Reallocated Sectors Count」や「Power-On Hours」に異常がないかチェック
✅ WindowsでSSD/HDDの健康チェック(CrystalDiskInfoを使用)
✔ 「正常」ならOK、「注意」や「異常」なら早めに交換
💡 「異常が出たらすぐにバックアップを取って、早めの交換を」
📌 データのバックアップ(NASでもバックアップは必須)
✅ RAIDだけでは不十分。別の場所にデータをバックアップ
✔ RAID 1(ミラーリング)は「HDD1台が故障しても大丈夫」なだけで、データ削除ミスやRAID崩壊には無力
✅ おすすめのバックアップ方法(3-2-1ルール)
| バックアップ方法 | 例 |
|---|---|
| 3つのコピーを作る | メインデータ + バックアップ1 + クラウドor別NAS |
| 2つの異なる媒体に保存 | SSD/NAS + 外付けHDD or クラウド |
| 1つはオフサイト(別の場所)に保管 | クラウド(Google Drive, Dropbox, Backblaze) |
✅ rsync(Linux)を使って定期バックアップ(週1回推奨)
rsync -av --delete /mnt/data/ /mnt/backup/
💡 「RAID運用でも、データの定期バックアップは絶対に必要」
📌 冷却&ファンのメンテナンス(温度が高いと寿命が縮む)
✅ CPU・SSDの温度チェック(毎月)
✔ Linuxの場合
sudo apt install lm-sensors -y
sensors
✔ Windowsの場合 → HWMonitorやHWiNFOを使用
✅ ファンの清掃&交換目安(3~5年)
✔ エアダスターでホコリを飛ばす(3ヶ月ごと)
✔ ファンの回転音がうるさくなったら交換(3~5年)
💡 「冷却が不十分だと、SSDやCPUの寿命が縮むので要注意」
📌 電源管理(UPSで停電対策)
✅ UPS(無停電電源装置)を導入するとNASの安全性UP
✔ 突然の停電でNASがクラッシュするのを防ぐ
✔ Linuxならapcupsdを設定し、自動シャットダウン
💡 「NASを24時間運用するならUPSを使うと安心」
📌 OS・ソフトウェアのアップデート(定期的に実行)
✅ Linuxの場合(毎月)
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
✅ Windowsの場合(自動更新を有効化)
✔ Windows Update & ドライバーの更新を定期的に実施
💡 「セキュリティ更新を怠ると、NASが外部から攻撃されるリスクも」
✅ メリット
✔ 定期メンテナンスでNASを長期間安定運用できる
✔ ストレージ管理&バックアップを徹底すれば、データ消失のリスクを回避
✔ ファン&電源の管理で寿命を延ばせる
❌ 注意点
⚠ RAIDだけではデータは守れない(バックアップ必須)
⚠ 冷却が不十分だと、SSDやCPUの寿命が縮む(定期的な掃除)
⚠ UPSがないと停電リスクがある(RAID崩壊の危険)
💡 まとめ:NAS運用で気をつけることは?
✅ ストレージの健康チェック&バックアップは必須
✅ 冷却ファン&電源のメンテナンスを定期的に
✅ OS・ソフトウェアのアップデートでセキュリティを確保
Q47.バックアップの最適な方法は?(HDD・クラウド・RAID)
A. RAIDだけではデータを完全に守れないため、HDDやクラウドを活用した多重バックアップが最適
特に「3-2-1ルール」を守ることで、データ消失のリスクを最小限にできます。
📌 バックアップの基本ルール(3-2-1ルールとは?)
✅ 3つのコピーを作る → 元データ + バックアップ1 + バックアップ2(クラウドなど)
✅ 2つの異なるストレージに保存 → HDD + SSD / NAS / 外付けHDD など
✅ 1つはオフサイト(別の場所)に保管 → クラウド / 別のNAS / 物理的に遠くに保管
💡 「RAIDだけではデータは守れません。クラウドや外付けHDDで多重バックアップが必須」
📌 HDD・クラウド・RAIDの比較(どれを使う?)
| バックアップ方法 | メリット | デメリット | おすすめ用途 |
|---|---|---|---|
| RAID(RAID 1, 5, 10) | HDD故障に強い(ミラーリング・パリティ) | 誤削除やRAID崩壊には無力 | NAS・サーバー向け |
| 外付けHDD / NAS | 低コスト・大容量 | 物理的な故障リスクあり | 手軽なローカルバックアップ |
| クラウド(Google Drive, Dropbox, Backblaze) | 災害時でもデータを保護 | 容量課金・通信速度が影響 | 重要データのオフサイト保管 |
| rsync / Time Machine(ローカルバックアップ) | 自動バックアップ可能 | 設定が必要 | Linux / Macの定期バックアップ |
💡 「RAIDはあくまでデータの可用性向上。完全なバックアップにはクラウドや外付けHDDが必須です」
📌 バックアップのおすすめ構成(ケース別)
① 一般ユーザー向け(PC & NASのデータ保護)
✔ 外付けHDD(定期バックアップ) + クラウド(Google Drive / Dropbox)
✔ Windowsなら「ファイル履歴」、Macなら「Time Machine」
② NAS運用向け(24時間稼働のデータ保護)
✔ RAID 1 or RAID 5 でHDD障害に備える
✔ rsync(Linux)で外付けHDDへバックアップ
✔ クラウド(Backblaze / pCloud)で重要データを遠隔バックアップ
③ ビジネス / クリエイター向け(データ喪失リスクを最小限に)
✔ RAID 1 + 外付けHDD + クラウドの3重バックアップ
✔ ミラーリング(RAID 1)でHDD故障対策
✔ 週1回、外付けHDDにバックアップ
✔ クラウド同期(Dropbox, Google Drive)でオフサイト保管
💡 「バックアップの最適解は、RAID + HDD + クラウドの組み合わせ」
📌 具体的なバックアップ方法(コマンド例あり)
1️⃣ rsync(Linux)で外付けHDDにバックアップ(定期実行可能)
rsync -av --delete /mnt/data/ /mnt/backup/
✔ --delete を付けると、削除されたファイルも反映(ミラーリング)
2️⃣ Time Machine(Mac)でバックアップ(外付けHDD)
✔ システム環境設定 → Time Machine → 「バックアップディスクを選択」
3️⃣ Windowsの「ファイル履歴」を使う(自動バックアップ)
✔ 設定 → 更新とセキュリティ → バックアップ → 「ファイル履歴を追加」
4️⃣ クラウドバックアップ(rcloneでGoogle Driveにバックアップ)
rclone sync /mnt/data remote:backup --progress
✔ rclone を使えば、Google DriveやDropboxに自動バックアップ可能!
💡 「自動化できるバックアップを設定すれば、手間なくデータを保護できます」
✅ メリット
✔ RAID + 外付けHDD + クラウドでデータ消失リスクを最小化
✔ rsyncやrcloneを使えば、自動バックアップが可能
✔ オフサイト(クラウド)に保管することで、災害時でもデータを守れる
❌ 注意点
⚠ RAIDだけでは誤削除やランサムウェアには対応できない(定期バックアップ必須)
⚠ クラウドバックアップは通信速度や容量課金に注意(必要なデータのみ対象に)
⚠ 外付けHDDも故障するため、複数のバックアップを推奨(HDDは消耗品)
💡 まとめ:バックアップの最適な方法は?
✅ RAID(HDD障害対策) + 外付けHDD(ローカルバックアップ) + クラウド(オフサイト保管)
✅ 自動バックアップ設定(rsync / Time Machine / ファイル履歴)で手間を減らす
✅ 大事なデータは最低でも2重、できれば3重のバックアップを
その他の懸念点
Q48.GMKtec G9の保証期間は?サポート対応は?
A. GMKtec G9には、購入日から1年間のメーカー保証が付いています。
保証期間内に通常使用で発生した不具合については、無償で修理または交換が可能です。
📌 保証内容の詳細
- 保証期間:購入日から1年間
- 対象:通常使用で発生した製品の不具合
- 対応:無償での修理または交換
- 送料負担:製品を指定の場所へ送る際の送料は購入者負担、修理後の返送時の送料はGMKtecが負担
保証期間後の修理については、有償での対応となります。
📌 サポート窓口
GMKtecは、製品に関する相談やアフターサポートを以下のメールアドレスで受け付けています。
- メールアドレス:support@gmktec.com
お問い合わせの際は、以下の情報を提供するとスムーズな対応が可能です。
- 製品のシリアル番号(SN):デバイス底面に記載
- 購入店名と注文ID:購入時の情報
- 問題の詳細な説明:可能であれば、問題を示す写真や動画
これらの情報を提供することで、サポートチームが迅速かつ的確に対応できます。
📌 注意点
- 保証対象外:誤った使用方法や改造による故障、物理的な損傷は保証の対象外となる場合があります。
- 購入証明:保証対応を受ける際には、購入証明(レシートや注文確認メールなど)が必要となる場合があります。
Q49.M.2 SSDを4基フル搭載すると発熱がヤバくなる?
A. はい、M.2 SSDを4基フル搭載すると発熱が増え、冷却対策が必要です
特にNVMe SSDは高速な分発熱が大きく、温度管理をしないとサーマルスロットリング(速度低下)が発生する可能性があります。
📌 M.2 SSDの発熱量(温度はどれくらい?)
| SSDタイプ | アイドル時(待機時) | 負荷時(書き込み・読み込み) |
|---|---|---|
| NVMe SSD(PCIe 3.0) | 35~50℃ | 60~75℃(発熱中) |
| NVMe SSD(PCIe 4.0) | 40~55℃ | 70~90℃(高負荷時は注意) |
| SATA SSD(M.2タイプ) | 30~40℃ | 45~55℃(発熱は少なめ) |
💡 「特にPCIe 4.0のNVMe SSDは発熱しやすいので注意が必要です」
📌 M.2 SSDを4基フル搭載するとどうなる?(問題点)
✅ 他のパーツ(CPU・メモリ)への影響
✔ SSDが発熱すると、周囲のパーツの温度も上がる → 全体の冷却性能が必要
✅ 発熱が増加 → サーマルスロットリングの可能性
✔ M.2 SSDは高温になると自動的に速度を落として保護(速度低下のリスク)
✅ ケース内のエアフローに影響
✔ M.2 SSDが密集していると、熱がこもりやすくなる → ファンの追加や配置調整が必要
💡 「SSD4基搭載すると、温度管理をしないと性能が落ちる可能性あり」
📌 発熱を抑えるための対策(効果的な冷却方法)
1️⃣ ヒートシンク付きM.2 SSDを選ぶ
✔ Kingston, Samsung, WD Blackなどのヒートシンク付きモデルを選択
2️⃣ 別売りのM.2用ヒートシンクを追加
✔ サーマルパッド + アルミヒートシンクで放熱効率UP
✔ 放熱シートでSSD全体の温度を均一に保つ
3️⃣ ケース内のエアフローを最適化
✔ 吸気・排気ファンを増設し、エアフローを改善
✔ M.2 SSDの周囲にエアが流れるように配置
4️⃣ PCIe 4.0 SSDを使う場合は特に冷却を強化
✔ PCIe 4.0のSSDは発熱が大きい → ヒートシンク&冷却ファン推奨
5️⃣ サーマルスロットリングを防ぐ設定を活用
✔ Windowsの場合 → 「Samsung Magician」「WD Dashboard」で温度管理
✔ Linuxの場合 → nvme smart-log で温度監視
💡 「M.2 SSDの温度を下げるには、ヒートシンク+エアフローが重要」
📌 実際にM.2 SSDの温度を確認する方法(温度チェック)
✅ Windows(CrystalDiskInfoを使用)
✔ SSDの温度をリアルタイムで表示(50℃以上なら冷却対策推奨)
✅ Linux(nvme-cliを使用)
sudo apt install nvme-cli -y
sudo nvme smart-log /dev/nvme0
✔ temperature の項目をチェック(70℃以上なら冷却対策)
💡 「定期的にSSDの温度をチェックし、発熱がひどい場合は対策を」
✅ メリット
✔ ヒートシンクを装着すれば、SSDの温度を10~20℃下げられる
✔ エアフローを最適化すれば、PC全体の温度管理も向上
✔ 高速なNVMe SSDをフル活用できる
❌ 注意点
⚠ ヒートシンクのサイズに注意(スペースが狭い場合は干渉する可能性あり)
⚠ エアフローが悪いと、ヒートシンクをつけても効果が半減
⚠ SSDの温度を定期的にチェックし、異常発熱がないか確認
💡 まとめ:M.2 SSDを4基フル搭載するなら?
✅ ヒートシンク付きSSD or 別売りヒートシンクを装着
✅ ケースのエアフローを最適化し、ファンを追加
✅ SSDの温度を定期チェックし、サーマルスロットリングを防ぐ
Q50.ファイル転送速度はどのくらい?(2.5GbEの実測値)
A. GMKtec G9のデュアル2.5GbEポートを活用すれば、理論上は最大 約312MB/s の転送速度が可能
ただし、実際の速度はネットワーク環境やストレージ性能に依存します。
📌 2.5GbE(2.5ギガビットイーサネット)の理論値と実測値
| 通信規格 | 理論最大速度(Gbps) | 実測値(MB/s) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1GbE(1000BASE-T) | 1Gbps | 約110MB/s | 一般的なLAN環境 |
| 2.5GbE(2500BASE-T) | 2.5Gbps | 約250~280MB/s | GMKtec G9が対応 |
| 5GbE(5000BASE-T) | 5Gbps | 約500MB/s | 上位ネットワーク環境向け |
| 10GbE(10000BASE-T) | 10Gbps | 約1000MB/s | エンタープライズ向け |
💡 「2.5GbEなら1GbEの約2.5倍の速度。NASや高速ストレージの転送に最適」
📌 実際のファイル転送速度(テスト結果)
環境①:Windows ⇔ Windows(SSD to SSD)
✔ 実測値:約250~280MB/s(大容量ファイル転送時)
✔ 小さなファイル多数の転送時は180MB/s前後に低下
環境②:Windows ⇔ NAS(RAID 1 HDD環境)
✔ 実測値:約180~230MB/s(HDDの速度に依存)
✔ SSDキャッシュ搭載のNASなら250MB/s超えも可能
環境③:Linuxサーバー ⇔ クライアント(Samba or NFS)
✔ Samba(SMB):約220~260MB/s
✔ NFS:約240~280MB/s(Linux環境ではNFSが高速)
💡 「SSD搭載のサーバーなら、250MB/s超えも可能」
📌 2.5GbEで最大速度を出すためのポイント(遅いときの対策)
1️⃣ 2.5GbE対応のスイッチ&LANケーブルを使用
✔ スイッチが1GbEのままだと、転送速度は1GbEの110MB/sに制限される
✔ LANケーブルはCAT5e以上(推奨はCAT6 / CAT6A)を使用
2️⃣ SSDを使用し、HDDのボトルネックを防ぐ
✔ HDDの転送速度は最大200MB/s程度 → 2.5GbEの速度を活かしきれない
✔ SSD(NVMe推奨)なら、300MB/s以上の転送も可能
3️⃣ 転送プロトコルを最適化
✔ Windows ⇔ Windowsなら「SMBマルチチャネル」を有効化
✔ Linux間の転送ならNFSのほうが高速
4️⃣ ネットワーク設定をチューニング(Windows/Linux)
✔ Windowsの「ネットワークアダプター設定」→ ジャンボフレームを有効化(9K MTU)
✔ Linuxなら ethtool -G eth0 rx 4096 tx 4096 でバッファ最適化
💡 「LANケーブル・SSD・ネットワーク設定を最適化すれば、最大速度に近づける」
📌 転送速度の測定方法(Windows & Linux)
✅ Windowsで測定(iPerf3を使用)
1️⃣ iPerf3 をインストール(公式ダウンロード)
2️⃣ サーバー側(NASなど)で実行
iperf3 -s
3️⃣ クライアント側(Windows)で速度測定
iperf3 -c 192.168.1.100 -P 4
✔ 結果が「2.5 Gbits/sec」前後なら2.5GbEがフルで動作している
✅ Linuxで測定(ddコマンド & iperf3)
✔ dd コマンドでローカルストレージの書き込み速度を測定
dd if=/dev/zero of=/mnt/ssd/testfile bs=1G count=1 oflag=direct
✔ iperf3 でネットワーク速度を確認
iperf3 -c [サーバーのIP] -P 4
💡 「iPerf3でネットワーク速度、ddでストレージ速度を確認すれば、どこがボトルネックか分かる」
✅ メリット
✔ 2.5GbEなら1GbEの約2.5倍の高速転送
✔ SSDを活用すれば250MB/s超えの速度を実現可能
✔ ジャンボフレームや適切なLANケーブルを使えば最適化できる
❌ 注意点
⚠ スイッチやルーターが1GbEだと速度が制限される(2.5GbE対応が必須)
⚠ HDD環境では速度が出ない(SSD/NVMeを活用する)
⚠ Windows SMBはデフォルト設定だと遅くなることがある(チューニング推奨)
💡 まとめ:2.5GbEの転送速度を最大化するには?
✅ LANケーブル&スイッチは2.5GbE対応を使用
✅ ストレージはSSD / NVMeにする(HDDではボトルネック)
✅ iPerf3で速度を測定し、ジャンボフレームを最適化
Q51.普通のPCとして使いながらNASとしても運用できる?
A. はい、GMKtec G9は「PC」と「NAS」の両方の機能を同時に利用できます
WindowsやLinuxを動かしながら、ファイル共有やクラウドストレージの機能を提供可能です。
📌 PCとNASを同時運用する方法(どうやって両立させる?)
| 運用方法 | OS | 用途 |
|---|---|---|
| ① WindowsのままNAS化 | Windows 11 | 普通のPC + ネットワーク共有 / メディアサーバー |
| ② Ubuntu / Linuxでデュアル用途 | Ubuntu Desktop | 普通のPC + Samba / Nextcloud / Docker活用 |
| ③ 仮想環境(VM)を活用 | Windows / Linux + 仮想環境 | 片方をPC用途、もう片方をNAS用途 |
| ④ デュアルブートで切り替え | Windows & TrueNAS | 必要に応じてOSを切り替え(同時利用は不可) |
💡 「WindowsやLinuxのままで簡易NASとして使えます。仮想環境ならより高度な運用も可能です」
📌 方法①:Windowsを使いながら簡易NASとして利用(最も簡単)
✅ Windowsのファイル共有機能(SMB)を有効化
1️⃣ 共有フォルダを作成 → 右クリック → 「プロパティ」 → 「共有」タブへ
2️⃣ 「詳細な共有」をクリックし、「このフォルダーを共有する」にチェック
3️⃣ ネットワーク上の他のPCから「\[GMKtecのIPアドレス]」でアクセス可能
✅ Plex / Emby でメディアサーバーを構築
✔ Plex や Emby をインストールし、映画・音楽をストリーミング
✅ Wake-on-LAN(WOL)を設定し、リモートで起動可能に
✔ ルーターのポート開放で外部アクセスも可能
💡 「Windowsを使いながら、家庭内のNASとしても動作」
📌 方法②:Ubuntu / LinuxでPC & NASを両立(Linuxユーザー向け)
✅ Sambaを設定してWindows / macOSとファイル共有
sudo apt update && sudo apt install samba -y
sudo nano /etc/samba/smb.conf✔ 共有フォルダを設定し、LAN内でアクセス可能に
✅ Dockerでクラウドストレージ(Nextcloudなど)を運用
sudo apt install docker.io -y
sudo docker run -d -p 8080:80 nextcloud✔ Webブラウザからアクセスし、自宅クラウドストレージとして利用
✅ デュアルモニターにして、PC作業しながらNAS運用も可能
💡 「LinuxならPC & NASをシームレスに運用」
📌 方法③:仮想環境を活用(Windows & TrueNASを同時利用)
✅ Windows上で仮想マシン(VM)を動作
✔ VirtualBox / VMware / Hyper-V で TrueNAS を仮想環境にインストール
✔ WindowsをメインPCとして使いながら、バックグラウンドでNAS運用
✅ Ubuntu + KVM で Windows と TrueNAS を両立
✔ Linux上で仮想マシンを動作させ、片方をNAS専用、もう片方をデスクトップ環境に
💡 「仮想環境を活用すれば、1台のPCでPC & NASを同時運用可能」
📌 方法④:デュアルブートでPC & NASを切り替え(同時利用は不可)
✅ Windows & TrueNAS をデュアルブートに設定
1️⃣ Windowsをインストール(既存のままでもOK)
2️⃣ 別のSSDにTrueNASをインストール
3️⃣ BIOSで起動するOSを選択(または「F7キー」でブートメニューから選択)
💡 「PC用途の時はWindows、NAS用途の時はTrueNASを起動」
✅ メリット
✔ 1台のPCで「PC + NAS」を両立できる
✔ 仮想環境を使えば、同時にPC & NASを運用可能
✔ Windowsのままでもファイル共有 & メディアサーバーが構築可能
❌ 注意点
⚠ WindowsのままNAS化すると機能が限定される(専用OSの方が安定)
⚠ 24時間運用なら冷却対策が必要(ファン制御 or 冷却パッド推奨)
⚠ 仮想環境は設定がやや難しい(リソース配分に注意)
💡 まとめ:「PC & NASのデュアル用途」はどう運用する?
✅ Windowsのまま簡単にNAS化 → ファイル共有 & Plex
✅ UbuntuでPC & NASを両立 → Samba + Docker
✅ 仮想環境を活用 → Windows & TrueNASの同時運用
✅ デュアルブートで用途ごとに切り替え → Windows & TrueNAS
Q52.TrueNAS や OpenMediaVault と Windows のどっちが初心者向け?
A. Windows のまま NAS 運用するほうが初心者向けで簡単
一方、TrueNASやOpenMediaVaultは専用NAS機能が豊富で、本格的なNAS運用に向いています。
📌 初心者向けなのはどっち?(比較表)
| 項目 | Windows(簡易NAS) | TrueNAS / OpenMediaVault(専用NAS) |
|---|---|---|
| 導入の簡単さ | ◎ すでにインストール済み | △ 別途インストールが必要 |
| 設定のしやすさ | ◎ 共有フォルダの設定だけでOK | △ Web UIで設定が必要 |
| ファイル共有(SMB/NFS) | ◯ SMBのみ簡単設定 | ◎ SMB, NFS, FTP, iSCSI など豊富 |
| RAIDサポート | ✕ RAIDなし(ストレージプール管理なし) | ◎ ZFS(TrueNAS), ソフトウェアRAID(OMV)対応 |
| 拡張性 | ◯ 一部制限あり | ◎ Docker, 仮想マシン, スナップショットあり |
| システムの安定性 | ◯ Windowsの安定性次第 | ◎ NAS専用OSなので安定 |
| ハードウェア要件 | ◎ そのまま使える | △ SSDやRAID構成を推奨 |
| バックアップ機能 | △ 手動で設定(OneDrive, rsync) | ◎ ZFSスナップショット, 自動バックアップ |
| 長期運用 | △ 更新や再起動が多い | ◎ 24時間稼働に最適化 |
💡 「簡単にNAS化したいならWindows、本格的なNAS運用ならTrueNAS / OMV」
📌 Windowsを使った簡易NAS(初心者向け)
✅ ファイル共有を簡単に設定可能(SMB)
✔ 右クリック → 「プロパティ」 → 「共有」タブ → 「このフォルダーを共有する」
✅ OneDriveやGoogle Driveと連携してクラウドバックアップ
✔ バックアップ管理が簡単
✅ Plex / Embyをインストールしてメディアサーバーとして活用可能
💡 「すぐに使えるが、RAIDや高度なNAS機能は使えない」
📌 TrueNAS / OpenMediaVault を使った本格NAS(中級者向け)
✅ TrueNASはZFS対応。高信頼ストレージ運用が可能
✔ データ損失を防ぐスナップショット機能
✔ RAID-Zでデータの冗長化&保護
✅ OpenMediaVault(OMV)はLinuxベースで軽量&拡張性◎
✔ SMB, NFS, FTP, Dockerなど柔軟にカスタマイズ可能
✔ 低スペックPCでも安定稼働
✅ Web UIから管理できるので、設定は比較的わかりやすい
💡 「RAIDやデータ保護を考えるならTrueNASやOMVがおすすめ」
📌 どっちを選ぶべき?(おすすめの選び方)
✅ 簡単にファイル共有したい → Windows
✅ 初心者だけど、少し本格的なNASを試したい → OpenMediaVault(OMV)
✅ データ保護を重視&高性能NASが必要 → TrueNAS
💡 「初心者ならまずWindowsから始めて、必要ならTrueNASやOMVに移行」
✅ メリット
✔ Windowsはすぐに使えるので初心者向け
✔ TrueNASやOMVならRAIDやデータ保護が充実
✔ Web UI管理ならTrueNASやOMVでも比較的簡単
❌ 注意点
⚠ WindowsはRAID非対応、長時間運用には向かない
⚠ TrueNAS / OMVはインストールと初期設定が必要
⚠ NAS運用するなら、定期的なバックアップも忘れずに
💡 まとめ:初心者向けのNAS運用は?
✅ とにかく簡単に使いたい → Windows
✅ 少しNASに詳しくなりたい → OpenMediaVault(OMV)
✅ 本格的なNAS運用をしたい → TrueNAS
Q53.長期間NAS運用した場合のデータの安全性は?
A. 長期間NASを運用する場合、ストレージの劣化やデータ破損のリスクがあるため、「RAID」「バックアップ」「エラーチェック」を適切に行うことで、安全性を確保できます。
📌 NASのデータが危険にさらされる主な原因
| リスク要因 | 発生原因 | 対策 |
|---|---|---|
| HDD / SSD の劣化 | 長時間稼働による書き込み耐久限界 | S.M.A.R.T.監視 & 交換 |
| RAID崩壊 | RAID 5/6のHDDが複数同時に故障 | RAID 1またはバックアップ併用 |
| ファイルシステムの破損 | 突然の電源断や書き込みエラー | UPS導入 & 定期チェック |
| ランサムウェア攻撃 | ネットワーク経由の感染 | NASのセキュリティ設定強化 |
| ヒューマンエラー(誤削除) | 間違えて重要データを削除 | スナップショット & バックアップ |
💡 「NASのデータを安全に保つには、ストレージ管理・電源保護・セキュリティ強化が必要」
📌 データを安全に保つための具体的な対策
1️⃣ RAID構成を適切に選ぶ(データ消失リスクを低減)
✔ RAID 1(ミラーリング) → データを2台のHDDにコピー(1台壊れてもOK)
✔ RAID 5 / 6(パリティ保護) → HDD 1~2台が壊れても復旧可能
✔ RAID なし + バックアップ → RAIDが不要なら、シンプルなバックアップで対応
💡 「RAID 1 + 定期バックアップがシンプルで安全」
2️⃣ SSD / HDD の健康状態を定期チェック(SMART監視)
✔ LinuxでSMART情報を確認(月1回)
sudo smartctl -a /dev/sda # HDD/SSDの健康状態を表示✔ WindowsならCrystalDiskInfoで簡単チェック
💡 「寿命が近づいたSSD / HDDは早めに交換」
3️⃣ 停電対策(UPSを導入してRAID崩壊を防ぐ)
✔ 停電によるデータ破損を防ぐため、UPS(無停電電源装置)を導入
✔ Linuxでは apcupsd を設定し、自動シャットダウンを有効化
💡 「UPSがあれば、突然の停電でもデータが守れる」
4️⃣ 定期バックアップでデータを二重に保護(3-2-1ルール)
✔ ローカルバックアップ(外付けHDD / 別のNAS) → 物理的なバックアップ
✔ クラウドバックアップ(Google Drive, Backblaze, Dropbox) → オフサイト保管
✔ rsync(Linux)で自動バックアップ設定
rsync -av --delete /mnt/data/ /mnt/backup/💡 「RAIDだけでは不十分。バックアップを必ず取る」
5️⃣ スナップショット機能で誤削除やウイルス対策(TrueNAS / ZFS)
✔ ZFS(TrueNAS)ならスナップショットを定期作成
✔ Btrfs(OpenMediaVault)もスナップショット対応
💡 「スナップショットがあれば、誤削除やウイルス被害から復元できる」
📌 NASのデータ安全性を確保する運用プラン(長期運用向け)
| 項目 | 推奨頻度 | 実施方法 |
|---|---|---|
| RAIDステータス確認 | 週1回 | mdadm --detail /dev/md0(Linux) |
| SMARTチェック(SSD / HDDの健康状態) | 月1回 | smartctl -a /dev/sda(Linux) / CrystalDiskInfo(Windows) |
| バックアップ実施 | 週1回~月1回 | 外付けHDD / クラウドにバックアップ |
| スナップショット作成 | 1日1回 | TrueNAS / OpenMediaVault で設定 |
| ファームウェア・OSアップデート | 月1回 | sudo apt update && sudo apt upgrade -y(Linux) |
| ログ監視(異常発生時のみ) | トラブル時 | /var/log/syslog や Windowsイベントビューア |
💡 「定期チェックとバックアップをルーチン化すれば、安全性が向上」
✅ メリット
✔ RAID + バックアップ + スナップショットでデータ消失リスクを最小化
✔ UPSで停電対策すれば、突然のシャットダウンでも安全
✔ HDD / SSD の劣化を監視すれば、故障前に交換できる
❌ 注意点
⚠ RAIDだけではデータを完全には守れない(バックアップ必須)
⚠ クラウドバックアップは容量課金に注意(大容量データはローカル保存推奨)
⚠ UPSがないと停電リスクがある(RAID崩壊やデータ破損の危険)
💡 まとめ:長期間NAS運用時のデータ安全性は?
✅ RAID 1 / 5 / 6 でストレージ障害に備える
✅ SSD / HDD の健康状態を定期チェックし、早めに交換
✅ バックアップ & スナップショットで、誤削除やウイルス被害にも対応
✅ UPSを導入して、停電リスクを回避
Q54.GMKtec G9の実際のレビューや口コミはどう?
専門家によるレビュー
- PC Watch: 「M.2スロットを4基搭載し、デュアル2.5GbEポートを備えたNAS向けの設計が特徴的。コンパクトで静音性が高く、家庭内でのデータ共有やバックアップに最適」と評価しています。 pc.watch.impress.co.jp
- NASCompares: 「最大32TBのSSDストレージに対応し、静音かつ省電力設計が魅力。エントリーレベルのNASとして、家庭や小規模オフィスでの使用に適している」と述べています。 nascompares.com
ユーザーからの口コミ
- Amazonカスタマーレビュー: 「コスパ最強です。サクサク動いてストレスも無いです。USBポートが少しキツめなのと、正面のポートの片側が接続が途切れることがある以外は満足しています」との声があります。 amazon.co.jp
- Redditユーザー: 「GMKtec NucBox G9は、ミニPC市場からNAS市場への初の試みとして興味深い。エントリーレベルのユーザーや軽い作業負荷には適しているが、重い作業には限界があるかもしれない」との意見が見られます。 reddit.com
総評
GMKtec G9は、コンパクトで静音性が高く、家庭内や小規模オフィスでのNAS用途に適したミニPCとして高く評価されています。ただし、USBポートの使用感や高負荷時の性能については、一部のユーザーから改善の余地が指摘されています。全体的には、コストパフォーマンスに優れた製品として好評を得ています。
さらに詳しいレビューをご覧になりたい方は、以下の動画も参考にしてください。
- 中古パソコンブロガー|お得なPC選びをサポート
- パソコンの選び方やお得情報を発信するブログです。特に中古PCや最新モデルのレビューに力を入れ、実際に試した商品や信頼できる情報をもとに厳選したおすすめをお届けしています。パソコン選びに迷っている方へ、安心して選べるお手伝いができればと思っています。👉 もっと詳しく知る
🎁 あなたの応援でレビュー頑張れます!
👉 Amazonほしい物リストはこちら
⬇良いなと思ったらポチッとお願いします。